『あと五分で京都、京都に到着いたします』
雑誌を見ながらボンヤリしていると、新幹線のアナウンスが聞こえてきた。
「あ〜あ、やっと着いたか。九州の小倉から四時間くらいといっても、やっぱり遠いよな」
大きなアクビをしながら出口へと向った。車窓からは京都の町並が見え、背の低いビル群にまじって歴史を感じさせる建物が見え隠れしている。
「あっ、東寺の五重の搭だ、懐かしいな」
列車の動きに合わせて、五重の搭は、左から右へと動く。
やがて新幹線はプラットホームに滑り込み、ドアが開くとともに、途端に冷たい空気が全身を覆う。三月になったとはいえ、京都はまだ寒い。おまけに駅の中はどっちを向いても、凄い人ごみである。
「こりゃたまらん! 早く人気のない所に行きたい」
僕はそそくさと八条口側の改札を抜けた。
京都を訪れるのは六年ぶりの事だ。
僕は佐伯光司、独身でしかも現在失業中である。暇を持て余して、こうして京都までフラフラしにきた訳だ。一度でいいから先に何の目的もない、自由気ままな旅をしてみたかった。少しばかりの貯金を下ろしてきただけなので、贅沢こそできないが…。少なくとも時間だけはふんだんにある。それにまだ二十五才だ! 一度くらいは失敗してもやり直しが効くと思っている。
「さてと、どこから見て行くかな。取りあえず、そこの東寺からかな」
僕は手元にある、京都のガイドブックをパラパラとめくった。
「しかし、家を出る時間が遅かったせいか、もう夕方だな」
駅を出て顔を上げると空は一面、夕焼け色に染っていた。やがて五重の搭が周囲のビルや住宅に挟まれるように見えてきた。そこまで来ると駅前の慌ただしさとはうって変わり、静かで落ち着いたムードの空間が開けていた。拝観料を入口で払うと、まず五重の搭を目指して進む。砂利を踏む音が足下で響く。
夕日と搭が重なった所で僕は立ち止まった。
「う〜ん。やっぱり夕日をバックにすると、この建物は映えるなあ」
バッグから一眼レフのカメラを取り出すと、ファインダーを五重の搭に向け、二、三枚シャッターを切る。
「そうだ! 今日は月が出るのを待っていようかな。どうせ急ぎの旅ではないからな」
地面にペタンと座り込むと、小型の三脚にカメラをつけて月が出るのを待った。
「ん? そういえばここの拝観時間は何時までだっけ?」
ちょっと気になったが、すぐに僕はカメラの調整を始めていた。暫くすると月がゆっくりと昇ってきた。月明りの中でカメラのシャッター・スピードや絞りを調整する。
「さあてと、こんなアングルでいいかな」
 どんな写真になるか、頭の中にイメージしながらファインダーを覗き込んだ。が、どういう訳か警告マークが点滅しているのだ。メカにはあまり詳しい方ではないが、こういう時は普通、撮影の限界値を超えている。それくらいの事は経験上知っていた。
どんな写真になるか、頭の中にイメージしながらファインダーを覗き込んだ。が、どういう訳か警告マークが点滅しているのだ。メカにはあまり詳しい方ではないが、こういう時は普通、撮影の限界値を超えている。それくらいの事は経験上知っていた。
「おかしいな? 何がいけないんだ?」
慌てて各部をチェックしたが、別におかしなところは見当たらなかった。
「ちぇ! 故障してるのかなあ。やっぱり中古は買うべきじゃなかったかな」
そう呟きながら顔を上げた時、五重の搭と重なった月は驚く程赤く染って見えた。
「変だなあ、何かの天文現象かな?」
太陽光の関係で月が赤い時もあるというが、それにしても赤すぎる。まるで血のような色である。気がつくと東寺の五重の搭も、講堂も金堂も、真っ赤な血の色に染っていた。
僕は妙な胸騒ぎを感じて後ずさりした。そして再び五重の搭を見た時、信じられない光景を目にした。
「うわああ! 血だ。血が流れてる!?」
搭の上から下へ滝のように流れている。後から後から湧き出るように。そしてその搭の最上部の屋根の上にはなんと人影があった。
「だ、誰だ?」
慌ててレンズを標準から二百ミリの望遠に換えて覗いた。
「何だ? ありゃ!」
僕は思わず叫んだ。ファインダーを通して見たそれは、とても人間とは思えなかった。全身が真っ赤で体長が三、四メートルはあるだろうか? 歌舞伎役者のような金色の髪を振り乱し、頭の上からは大きな角が二本、突き出ている。
「まさか! 鬼?」
人を驚かそうとして誰かがイタズラしているのか? でもあの五重の搭は六十メートル近くある筈だ。イタズラであんな所に登るとも思えない。もし落ちたら間違いなく即死だ。震える手でカメラをバッグに戻すと、僕は東寺の講堂の中に走っていった。
「すいませ〜ん! 誰かいませんか〜?」
叫び声が虚しく建物の中に反響する。妙な事に講堂の中には誰もいないようだった。
金堂の方にも行ってみたが、やはり同じ事だった。
「おかしいな、まるで人の気配がない。寺の管理人はどこだろう?」
再び、東寺の中庭に出た。
「あれ?」
一体、どうしたのだろうか? 今まで真っ赤だった月は元の色に戻っている。周囲を見渡すと血が流れていた五重の搭も、僕の目の前に何事もなかったかの様にひっそりと立っていた。
「おかしいなあ。目の錯覚だったかな?」
茫然としていると不意に遠くから町の音が聞こえてきた。
「確かに搭には血が流れていたし、屋根には鬼がいたんだがなぁ。僕は疲れているのかな?」
しかし錯覚だったにせよ、どうしてあんなものが見えたのか? 僕は東寺を後にしながら、搭の方を、何度も何度も振り返って見た。今のは本当に幻覚だったのか?
首を傾げながら、東寺前の停留場から市バスに乗って、四条大宮まで出た。あれこれ考えながら四条通りを歩いていく。
「やっぱり警察に通報すべきかなあ。しかし狂人扱いされるのがオチだよな。うん、やっぱり目の錯覚に違いない! 少し疲れていたからな」
そう考えてなんとか一人で納得した。少し落ち着いてきたので、バッグからカメラを取り出すと、先斗町に向う事にした。四条大橋手前を左に折れて、鴨川沿いに歩く。やがてお茶屋の立ち並ぶ通りまで来ると、どこからか三味の音に交じって舞子の唄う祇園小唄が聞こえてきた。
「月はおぼろに東山〜」
きっとどこかの高級料亭で唄っているのだろう。障子越しにボンヤリとした灯りが見える。舞子さんが来るような店は高瀬川沿いにずらっと並んでいる。たくさんの川柳が夜風に揺れていた。
「舞子さんて普段はなかなか見られないんだよな。あんな所で粋な遊びをしてみたいもんだ」
貧乏な僕には無理な相談だ。思い直してカメラにフラッシュを取りつけ、今度は気紛れに袋小路にも入ってみた。京都には昔から家の柱を真っ黒に塗った家が多い。魔よけのためだろうか? それに注意して見ると結構、結界印のついた家がたくさんある。そのうち僕は先程の出来事も忘れ、夢中になってシャッターを切っていった。角を曲った所でカメラのカバーを開けてフィルムを交換し、次に向おうとした時、突然誰かに首根っこを掴まれた。
「コラ、兄ちゃん! なにしとんじゃワレ!」
見ると目の前にはチンピラかヤクザだろうか? 酔っ払った大男が立っていた。
「いえ、この辺の景色をですね」
「景色やと? 今のフラッシュで、ワシの目ぇ、ワヤになってしもうたで!」
「そんなあ! 言いがかりだ!」
「何やと? 面白い事言うやないか、兄ちゃん!」
男はドスの効いた声で怒鳴ると僕の胸倉を掴み、軽々と宙に持ち上げた。
「治療費、出してもらおやないか!」
「い、いえ、お金ないです」
「なに寝惚けた事ゆうとんじゃ! 壊したろかい!」
男に胸倉を掴まれたまま、はがいじめにされた。さんざん振り回されて、何度も塀や壁に叩きつけられる。衝撃を受ける度に意識が遠くなっていった。
「どや、金持ってる事思い出したやろ! 出すもん出さへんやったら、もっと歌わしたるど!」
男は酔っ払った顔で満足そうにニタリと笑った。
「まだ思い出さへんちゅうんか? しぶといガッキゃのお!」
男は片手で僕を押さえつけたまま、右手を振り上げる。
「舌噛みなや!」
その時、暗闇の方向から何かが飛んできた。ビシッ! と鋭い音がする。
「うぎゃ、あたたた! ほ、骨が」
途端に男は僕を地面に落とした。そのままうずくまって手を必死で押さえている。
僕の足下には小さな扇子が落ちていた。
「扇子?」
「なんじゃコラッ! ワシを誰や思うてんねん!」
トントントントントントントントントントン、闇の中から何かを打つような音が聞こえてきた。規則正しい音である。
「なななな、何やぁ?」
暗闇から聞こえてくるその音は段々と近づいてくる。やがてその地面を打つ規則正しい音は一段と大きくなった。
「な、何じゃ、こりゃ!」
男が大声をあげた。僕も痛む体を押さえながら、その音のする方向を見た。
暗闇から現れたのは一体の市松人形だった。その人形は鞠をトントントン、とつきながら静かにこっちに向って歩いてくる。やがて人形は僕とその男の前まで来ると、その足を止めた。
「なんで人形が歩いとんねん! 気色悪いやっちゃ!」
男はそう叫ぶと、いきなりそばに落ちていた棒を掴んで人形に飛びかかった!
バシュウウンンン! という音と共に一瞬、その人形が真っ白に光ったかと思うと、男は一気に五メートルぐらい弾き飛ばされていた。男の持っていた棒も真っ二つに割れて、男のそばに突き刺さっている。
「何やこいつはぁ! 化物や〜、ひ〜っ!」
酔っ払いの大男は悲鳴を上げながら逃げていった。僕はおそるおそる、その人形の方を振り返る。
「あれ、いない」
見るとその人形の着物の裾が、路地を曲っていくのが見えた。少々恐かったが、後を尾けていく事にした。どうして人形が歩けるのか? 僕を助けた人形はかなりの早さで歩いていく。どういう訳か全然追いつけない。
「おかしいな、何で走っているのに追いつけないんだ? ああっ!」
よくよくその人形の足元をよく見ると、足が地面についてないのが分かった。
「まさか、浮んでいるのか?」
普通の人間だったら、ここで悲鳴を上げて逃げる所だが、なぜか僕は妙な安堵感を覚えていた。不思議と恐い気持ちが湧いてこない。それよりもむしろその人形に対しての興味が増していくばかりである。人形はどんどん裏路地の方へ進んでいくが、とうとうどこをどう通ってきたのかも分からなくなってしまった。
「けげっ! 迷子になっちゃった!」
ふと、人形が進んでいる方向を見ると、奇妙な形をした空間が開けている。それはさまざまな色の光を放ちながら、暗闇の中をゆらゆらとゆらいでいた。
「亜空間?」
意味もなくそんなSFのような言葉が頭をよぎった。先を行く人形はピョンと飛び上がると、その少し口を開けた隙間にフワリと入っていった。
慌ててそこに飛びこむと、そこの中は一本の長いトンネルのようになっていた。色んな光があちこちに飛び交っている。その光をじっと見ていると、妙に懐かしい気持ちになった。トンネルの中を進んでいくとやがて前方にさらに別の空間が開けているのが見えてきた。思い切ってまたその中に飛びこむ。僕はそこで不思議な光景を目にして立ちつくした。
「あああ! 人形がこんなにたくさん!」
そこではたくさんの人形達が、鞠をついて遊んでいた。大きな人形、小さな人形、立っている人形、座ったままの人形、人形達は童唄のようなものを唄いながら、規則正しく鞠をついている。さっき僕を助けた人形も、そこでまた鞠をつき始めた。
「どうもカラクリ人形じゃなくて、本当に生きて動いているんだな、凄いや」
人形はただ鞠をついている。その様が可愛らしかったので、暫くその場にしゃがみこんで、童唄を聞いていた。
黒い鬼には角一本
赤い鬼には角ふたつ
山の天狗が言う事にゃ
鬼の魂、墓の中、墓の中
鬼の問答、答えなば
取って食われて骨一つ
鬼の魂、救えなば
取って食われて骨一つ
赤い月には赤い鬼
月のない日は黒い鬼
鬼の魂、救いたきゃ、
蛇の体を開けしゃんせ
あの娘可愛いや骨一つ
鬼の声を聞いたとさ
霞畑で骨一つ
取って喰われて骨一つ
山のおろちが言う事にゃ
鬼の魂墓の中
声を聞いても振り向くな
墓の中まで引き込まれ
取って喰われて骨一つ…
「こ、怖い」
歌の文句に心底怖くなるが、人形達はなおも唄い続けている。そのうち、さっきの人形がついている鞠が僕の方に、コロコロと転がってきた。人形はこちらへゆっくりと歩いてくる。鞠を取るとその人形に手渡した。
『ありがと』
「えっ? 喋れるのか?」
『ながく・生きて・いるから』
「君達は市松人形っていうんだろ?」
『そう』
「さっきは助けてくれて有難う」
『うん、あなたは・また・会うことに・なると思うから・助けたの』
「えっ、どういう事だい? なぜそんな事が分かるんだ?」
『ある・人から・聞いたの』
「ある人、だれだい? それは」
『いまに・わかるわ』
「えっ?」
ハッ、と我に帰った。
「あれ? ここは」
我に返り、周囲を見ると元の四条通りに戻っていた。再び人々のざわめきが思い出したように聞こえてくる。
「今のは一体?」
また幻覚だったのだろうか? それとも夢でも見ていたのか、暫し呆然としてしまった。
「もう、駄目だ。頭がフラフラする」
僕はそのまま呆然と立ちつくしたまま、意識が遠のいていくのがわかった。
次の日、夕方頃になってようやくホテルのベッド上で目を覚ました。意識のないまま、祇園ホテルという四条通りに面した老舗のホテルにチェック・インしたようだ。
「昨日の事は全部、夢だったのかな。しかしどうも気になるなあ」
ベッドから起き上がると、カーテンを開けて窓の外を見た。昨日と同じように空は真っ赤だった。
「よし、昨日と同じ所にもう一度、行ってみるか」
そう決心すると、食事もそこそこにホテルを出た。フロントの話だと昨日は、僕を部屋まで運ぶのが大変だったそうだ。思わず顔を赤らめる。
昨日と同じように四条通りをまっすぐに歩き、橋を曲って先斗町へと向い、再び夜になるのを待った。
「ひょっとしたら、昨日の市松と会えるかも知れないぞ」
喫茶店で時間を潰し、また月が昇ってくるのを確認すると、カメラを持って通りに出た。なるべく真っ暗な所を選んで通る。
「!」
角を曲った所で突然立ち止まった。見ると舞子が狭い露地をまっすぐに歩いていく。だらりの帯を下げて、心地好いぽっくりの音を鳴らしている。
「しめた! 写真を撮らせて貰おう!」
そう意気込むと、急いで舞子のそばに走り寄った。
「すみません、写真を撮らせて貰えませんか?」
「…」
しかし舞子は返事をしなかった。ただぽっくりをカラコロ引きずりながら歩いていく。
「あの、失礼なのは承知です。一枚でいいんです。」
突然、舞子の足が止った。なぜか機械のようにギギギ、と妙な音がする。
「あの? うわあああああ!」
膝がガタガタ鳴って動けない。
「そ、そんな馬鹿な!」
振り向いた舞子は等身大の人形だった。そのままこちらにギギギ、と軋む音を響かせながら近づいてくる。無表情な顔が少しずつ、残忍な顔に変わっていく。
『どないしはったん? 写真、撮りたかったんちゃいますのん? 佐伯光司はん』
「な、何で僕の名前を知ってるんだ?」
ドシュウウウウウ! という音と共に突然、舞子人形の体からは無数の腕と足が四方八方に伸びた。それが辺りの建物に突き刺さる。蜘蛛の巣のように舞子人形の体は張り巡らされ、完全に僕の周囲を覆ってしまった。
『ほほほほほ、逃がしまへんえ、あんたはんが干からびてしまいはるまで、その血、吸わせてもらいますえ』
「ひいいい、やめてくれ〜!」
無数の舞子人形の手足が、僕の体に突き刺さるようにして伸びてくる。
『ちっとも痛うあらしまへんえ〜!』
その時、舞子人形の背後の闇には、白い顔が浮び上がっていた。突然、闇の中から閃光が走る!
バシュウウウウウ! という音と光が目の前を走った。
「!」
気がつくと舞子人形の手足が束になって、幾つも地面に落ちてきた。僕は驚いて前方の闇を見つめた。
『どなたどす?』
慌てた舞子人形が怒鳴る。
『クスクスクス』
闇の中から笑い声が聞こえる。そして、再び僕の足下には小さな扇子が落ちてきた。
「あっ、昨日の市松か!」
『許さしまへんで〜!』
舞子人形の口が大きく開いた!
ボオオオオオオオオオ! という音が闇に走った! 間髪を入れず、舞子人形は市松の方に向って炎を吹いていた。市松は闇の中に姿を消すと月光の中にフワリと舞い上がり、隣の建物の屋根の上に舞い降りる。
『あんた、なんでうちの邪魔するねんな!』
『疾鬼の・部下である・おまえが・気にいらない・だけよ』
『よー言うわ! 裏切り者が!』
舞子人形の片手がズルリと地面に落ちた。中からはギラリと光った刀が姿を現す。
『裏切り者は、許さしまへん!』
舞子人形は大きくジャンプすると、屋根の上にいる市松に襲いかかった!
ドカアアアアアアア! という音が再び闇に走る。舞子人形が腕を振り下ろした瞬間、屋根の瓦がバラバラになって吹き飛んだ。しかし市松は瞬間的に、舞子人形の死角に回り込んでいた。
『遅いわよ』
『な?!』
ドキャアアアアアア! という音と共に、市松の手からは閃光が飛び出した。舞子人形は破片をまき散らしながら吹き飛んでいく。市松は大きくジャンプしながらその後を追った。
「ま、待ってくれよ!」
震える足を引きずりながら、懸命に後を追った。二つの人形は攻撃し合いながら既に、鴨川のほとりにまで来ていた。
『くそっ!』
舞子人形は必死になって、長い手足を振り回している。
『そろそろ・闇に・お帰り』
『何やて?』
やがて、シュウウウウウ! という音が辺りに響き渡る。市松は両手を宙で合せると、呪文を唱え始めた。続いて体中が一気に青い光に包まれる。
『ま、まさか!』
『鬼雷獣! 召喚!』
『や、やめておくれやすー!』
舞子人形が絶叫した。続いて市松の両手からは巨大なエネルギーが炸裂する。
ズガアアアアアアンンンンンンン! という音と共に、一気に周囲の視界が真っ白な光に包まれる。僕も勢いで吹き飛ばされた。
『ぎゃああああああ!』
舞子人形は悲鳴を上げ、燃え上がりながら鴨川の中に墜落していった。おびだしい水蒸気が辺りを包む。もうもうとした煙の中で市松は宙に浮いていた。
「今のは、何なんだ?」
ゆっくりと起き上がると、舞子人形の落ちた川に向って歩いた。そのまま中を覗き込む。
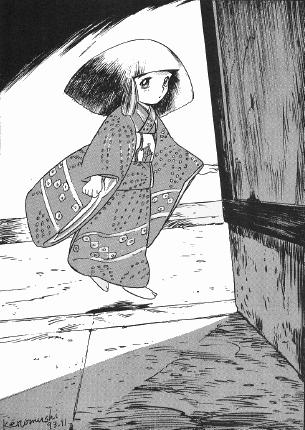 「うっ」
「うっ」
川の中にはさっきの怪物が真っ黒になって浮んでいた。まるで原形をとどめていない。そのまま破片が一つ一つ、川に流されていく。
「何てこった」
『驚いた?』
市松は少し首をかしげると、僕に言った。
「また、助けてくれたんだな。一体、何がどうなってんだ?」
『フフフ、またね』
市松は悪戯っぽく笑うと、闇の中に消えていった。
「おい、待ってくれよ!」
慌てて後を追いかける。
「誰を待ってくれだって?」
いきなりうしろから呼び止められた。
「えっ?」
驚いて振り返ると、そこには二人の男が立っていた。
「あ、何ですか?」
「警察の者です。ちょっと来ていただきたい」
一人の男はそう言うと、いきなり僕の手に手錠をかけた。
「あの、何なんですか? これ」
「見れば分るだろ。手錠だよ」
目の前の男が言う。
「何で僕が! 何にも悪い事はしてないぞ!」
「まあまあ、話は署でゆっくり聞くから。さあ、行こう」
二人の男に両側から腕を掴まれ、仕方なしに歩いた。
調べて貰えば分る事だ。そう思っていた。
歩いていくと、周囲にはヤジ馬が群がっていた。白い視線が突き刺さる。
パトカーの回転灯が見える所まで来ると、改めて惨めな気持ちになった。京都まで来てどうしてこんな事になるのだろうか? 僕達がパトカーに乗り込むと、一斉に周囲の人達が口々に罵りこぶしを突出した。
「死ね〜! 放火魔!」
「この異常者! 燃えた私の店どないしてくれるんや!」
パトカーの中で仰天する。
まさか、さっきの市松と舞子人形が闘った時に、そこら辺の家に火が燃え移ったのか?
「この連中は、僕が放火をしたと思っているのか?」
「そう言う事」
隣にいる男が僕の脇をつつきながら言う。
「そんな、とんでもない! 僕はただの旅行者だぞ!」
「しかし、現に目撃者がいるんだよ」
運転席に座っていた男が言う。
「目撃者?」
「ここら辺でいつも酒を飲んで問題おこしてるオッチャンだけどね。君が放火をしているといって、警察まできたんだ」
「オッチャン?」
昨日の大男の事を思い出した。
「まさか!」
「しかしあの男、珍しくケガしていましたね」
隣の男が言う。
「何でも手の甲の骨が折れていたってさ。どうせケンカでもしたんだろ」
昨日の腹いせだな。すぐにそう思った。
「それはそうと最後は随分、凄い爆発だったそうだな。どんな火薬を使ったんだ?」
「あれは放火でも、火薬を使ったんでもないんだ!」
「ほう、じゃあどうしてああなったんだ?」
「そ、それは」
言葉に詰った。どう言ったらいいのだろうか? まさか市松人形と巨大な舞子人形が闘って、ああなりましたなんていっても、狂人扱いされるだけだろう。とはいえこのままだと、自分は放火魔にされて、ヘタすると懲役を何年喰らうか分からない。
パトカーが走りだすと、周囲を囲んでいた人達も諦めて引っ込んだ。僕は遠くなる先斗町を見送りながらうな垂れた。
「どうすりゃ、いいんだ」
パトカーは僕が泊っている祇園ホテルの前を通って八坂神社に突き当たると、そこから北上を始めた。途中で角を曲ってしばらく行くと、右手に平安神宮が見えてくる。さらにパトカーはまっすぐに走り続ける。どういう訳か町から離れているようである。回転灯を消したパトカーは真っ暗な道を走り続ける。
「あの、警察はこっちなんですか?」
「いや、別に警察には行かないけどね」
「ええ?」
「平田君、そろそろいいだろ。手錠を外してやろう」
「はい、田村さん」
隣にいた男はそう言うと、僕の手にかかっていた手錠を外した。
「えっ、どうなってんの?」
「詳しい話は後でするけどね。あの場合、一応の芝居をした訳だ」
「芝居? じゃあ、僕を捕まえた訳じゃないんですか?」
「勿論、ある方に君を連れてくるように頼まれたんでね。おっと、一応私達は警官だよ。私の名前は田村、こっちは部下の平田刑事です」
「よろしく」
二人の男は僕に警察手帳を見せた。
「何だかさっぱり意味が分らない」
「無理もないよ。それよりも、やばい事になってきた」
運転している男の表情が突然、険しくなる。
「えっ?」
「平田君、拳銃出しとけよ」
「了解」
隣にいた男は懐から拳銃を取り出した。シリンダーを開けて弾が入っているかどうか確かめている。
「一体、何が始るんだ?」
「とにかく、じっとしていてくれ」
ドガッ! と鈍い音が走ると突然、パトカーの後部のガラスがバラバラになった。激しい振動が車体を走る。
「やっぱり、君は色んな化物に狙われる事になってんだな!」
「ええっ? どういう事なんだよ!」
『ケケケ、こんな所にいたぞ〜』
『ここにいたぞ〜』
『もう逃がしはしない、ケケケ』
どこからか、地獄の底から沸き上がってくるような声が聞こえてきた。震えたまま身をすくめる。
バリバリバリ! と次の衝撃がきた時には、パトカーの屋根が一気に剥がされていた。後ろを見ると紙切れのようになって屋根が飛んでいく。
「わあああ!」
「ちくしょう、オープンカーになっちまった。涼しいねえ!」
ハンドルを握りながら田村刑事が喚く。
「な、何だあれは!」
空を見ると、おびただしい数の奇妙な生き物が空を覆っていた。その生き物達は自ら真っ赤な光を放ち、渡りをする鳥のように群れていた。まるで巨大な赤い川が夜空に流れているようだ。それは溶岩かマグマの流れのように不気味な音を立てて、空一面に広がり、こちらに近づいてきた。
『殺せ〜』
『骨まで溶かしてしまえ〜』
『八裂きにしろ〜』
憎悪をかきたてるような声は、その赤い流れから聞こえていた。
「ちくしょう! やっぱりあいつか!」
横にいた平田刑事が叫ぶ。
ズズズズズズ! という不気味な音と共に、赤い流れの一部がパトカーを覆い始めた。銃を持った二人は続け様に拳銃を乱射したがいっこうにこたえた様子もない。奇怪な音を立てながらどんどんパトカーを覆っていく。僕はその流れを見て思わず悲鳴を上げた。一つ一つの流れは近くで見ると、化物の顔のような形をしている。それらがこっちに向って呪いの言葉を吐いていたのだ。僕は吐き気がして胃液が飛び出しそうになった。
「くっ、ハンドルが効かない!」
パトカーはどんどん、ガードレールの方に吸い寄せられていく。
「助けてくれ〜!」
ドガアアアンンンンン! と車体を揺さぶる激しい音がした。
パトカーはガードレールを突き抜けると、真っ逆さまに落下していく。それを待っていたかのように、赤い流れは一斉に襲いかかって来た。
『殺せ〜』
『骨までしゃぶれ〜! ケケケ!』
僕は薄れていく意識の中で、真っ赤な流れの中に巨大な口が開くのを見た。バックリと開いた地獄の口が襲いかかってくる。
「怪物め!」
『お前達は永遠に苦しみ続けるのだ〜!』
物凄いスピードで、怪物の口が目の前に迫った。
だが、怪物が僕達を飲み込もうとする刹那、パトカーはその空間から消えてしまった。赤い流れの怪物は大きく口を閉ざして空しく空を噛み、慌てて体勢を立て直した。
『消えた? 馬鹿な、どこに逃げた!』
確かに飲み込んだ筈の獲物はどこかに消えていた。
『うおおおおおおおおおおおおおお〜!』
怪物は怒りのあまり、もの凄い勢いで山の中に突っ込んでいく。周囲の木々がたちまち押し潰され、ドオオオオンンンンン! という激しい地鳴が夜空に響き渡った。
『どこに逃げた〜!』
荒れ狂う怪物をよそに、パトカーは別の場所に移動していた。
|
|