翌日、朝早く目が覚めた。食事はせずにホテルを出る。三十三間堂の事が気がかりで朝食どころではなかったのだ。朝日の中の祇園通りを歩く。祇園からバスに乗り、三十三間堂に向った。思ったより早く二十分くらいで到着した。拝観が始る八時までぶらぶらして時間をつぶし、開門と同時にあまり広くない入口から中に入った。砂利道をまっすぐに進んでいくと、全長百二十メートルの本堂が見えてきた。
「さて、来たのはいいがよくよく考えたら、待合わせの時間を聞いてなかったな。まあ待っていればおいおい来るだろう」
自分でも間抜けだと思いつつ、砂利の上をほっつき歩いた。やはり早すぎたのか、まだこの時間には誰も来ていないようだ。
ふと空を見るとにわかに曇り始めていた。
「雨になるかな? これは」
そう思ってボンヤリしていると、案の定パラパラと降ってきたので、慌てて本堂の中に避難した。すぐに止むかと思ったが、期待空しくザアアアアアアアアア!っと激しく本降りになってきた。
僕は千一体あるといわれる観音像の前で立ちつくして呻いた。
「あ〜あ、こりゃ身動き取れなくなったなあ」
ゆっくりと歩きながら、本堂の中を見て回る。だが、風神と雷神の像の前を通り過ぎた時、突然小さな声に呼び止められた。
『きのうは・無事に・逃げられたの?』
「えっ? ああ!」
驚いて振り返ると、風神の像の上には昨日、先斗町で僕を助けた市松が座っていた。
足をぶらぶらさせながら僕を見つめている。
「ああ、おかげで何とか逃げられたよ。本当に死ぬかと思ったけど。ところで今日は仲間の人形達は?」
『今日は・みんな・眠っているわ。それぞれの・家の中で』
「それぞれって、みんな別々の家からやってくるのか?」
『うん・時がきたら・ああやって・集まるの』
「なるほど、人形にも寄合いがある訳か。それより昨日お前達が唄っていた唄は何なんだ?」
『あれは・鬼の・唄なの。いにしえより・伝わる・鬼の唄』
「鬼の唄?」
『鬼に・喰われない・ための…』
「昔から鬼ってたくさんいたのか?」
『そう。あたしも・そのときから・生きている』
「なるほど、もしや、超常現象調査会のもう一人のメンバーって、お前の事だったのか」
『そうよ、まりちゃん・たちとは・少し・目的が・違うけど』
「目的が違う?」
『あたしの・目的は・別な・ところに・あるの。今日は・そのために・あなたを・呼んだ』
市松人形は、雨が降り続ける空を黙って見上げると、思い出すようにして喋り出した。
『あたしは・昔・妖怪や・鬼たちを・支配する・立場に・いたの』
「妖怪や鬼達を? じゃあお前は」
『そう。人間の・敵だった。闇の物たちと・いっしょに・人間界を・支配するために・おおくの・妖怪たちを・操ってきた』
「お前が?」
『人間たちは・あたしを・天魔の・ヒトガタと・呼んで・怖れていた。ところが・ある日・人間の・逆襲が・始まったの』
「人間がよく鬼に、逆襲できたな」
『逆襲・したのは・一人だけ。それも・お寺を・追放された・一人の・僧だった』
「お坊さんか。法力でも強かったのか?」
『そう、「善界」という・その僧は・恐るべき・力を・もっていた。妖怪で・あれに・かなうものは・いなかった』
「そんなに強いのに、どうして寺を追放されたんだ?」
『善界には・子供が・いたの。小さな・女の子が。それが・寺に・ばれて・善界は・追放された。破戒僧・として』
「法力の強い破戒僧か。お前はそいつとやりあったのか?」
『一度だけ・闘った。だけど・あたしは・とても・かなわなかった』
「よく殺されなかったな」
『そう、善界は・あたしを・殺さなかった。なぜか・ぎりぎりまで・追いつめた・あたしを・助けてくれた』
「助けた?」
『傷ついた・あたしを・家に・連れて帰って・くれた』
市松の思い出は過去へフィード・バックしていく。その魂は遥か昔のあの場所へ帰っていた。
「わあ! お父ちゃん、何? それ」
「お雪、お前の欲しがっていた人形さんだ。大事にしろよ」
「あれ? この人形、随分傷ついてるのね」
「ははは! さっきまで父ちゃんと闘っていたんだぞ! 父ちゃんの方が強かったが、その人形もかなりなもんだった!」
「変な父ちゃん! 嘘つきね」
「わっははは!」
「さあ、御飯にしますよ」
傷ついた人形を連れて、善界は我が家に戻って来ていた。娘の雪は市松人形を嬉しそうに抱いている。
「後で綺麗にして上げますからね、そうだ! 貴女の名前を考えなくちゃね!」
「お雪、そんなのは飯の後にしろよ!」
「駄目よ、この子も一緒に御飯を食べるの。ほったらかしじゃ、可哀そうじゃない!」
雪は市松を抱いたまま、ちゃぶ台の前に座った。
「あなたは何が好き? 何でも選んでいいのよ」
「人形が飯を食う訳ねえだろ?」
「食べるもん!」
食事が終わると、雪は母親と一緒に市松人形を修理した。破れた着物を縫い、削れた所は胡粉を塗り合わせて修復していく。何日かたって市松は元どおりになった。
「わあい! これで綺麗になったわ。お名前、何てつけようかな?」
「ほほう、綺麗になったじゃねえか! こうして見るとお前も結構、べっぴんさんだな? おい! 後はおてんばな所を直せよ!」
「また父ちゃんは変な事を言う! この子はそんな悪い子じゃないもん」
「ははは! 悪かった、そうだな。胡蝶ってのはどうだ? 猿楽(能)からとったんだけどよ」
「胡蝶? この子に合ってるわ! わあい、貴女は今日から胡蝶ちゃんよ!」
雪は胡蝶を抱き上げると、嬉しそうに飛び上がった。その時から胡蝶の顔には少しずつ優しさと微笑みが生まれた。
だが、その幸せも長くは続かなかった。ある日、善界が留守の間に鬼や妖怪達が母親と雪を襲ったのだ。
「お雪! お前だけでも早く逃げて!」
「お母ちゃん、駄目! お父ちゃんがすぐに帰ってくるわ」
『ケケケケ! 無駄な事よ! その小さな体を引き裂いてやるわ!』
ズガアアアンンン! と激しい音が家中に走る。鬼が雪に手をかけようとした瞬間、家中に目に見えない衝撃波が走った。化物は外へ吹き飛ばされた。
『な、何だと? 善界なのか?』
『お前達の・いいようには・させないわ』
『きさま! 蘭火ではないか! 生きていたのか?』
「蘭火?」
雪は驚いた。
「胡蝶ちゃんが動いてる。どうして?」
『ケケケ! これはお笑い草だ! かっては人間共を震え上がらせた、この天魔のヒトガタの蘭火が人間と一緒に暮らしているとはな!』
「嘘、そんなの嘘よ!」
『やい! 蘭火! こんな人間はさっさと殺して、我々と一緒に来るのだ!』
『それは・できない』
『何だと! きさま! 鬼芭王様を裏切るつもりか!』
『この子は・あたしの・命に・かえても・守ってみせる!』
『おい! こいつも殺してしまえ〜!』
何百という、妖怪や餓鬼達が一斉に襲いかかる、それはまさに地獄絵図だった。胡蝶はありったけの術と力を振り絞って闘った。たが、気がついた時には、雪と母親は既に死んでいた。
『ユキチャン』
舞い落ちては消えていく雪のように、雪は胡蝶の目の前で静かに言切れていた。
『蘭火! お前も死ぬのだ〜!』
ドンッ! と激しい音が胡蝶の体中を走る。だが、それは胡蝶に襲いかかった妖怪が砕ける音だった。振り向くとそこには善界が立っていた。
『善界!』
「うおおおおおおおおおおおおお〜!」
娘と妻が引き裂かれている姿を見て。半狂乱になった善界は全身から凄じい闘気を発して闘った。もはや善界は鬼と化していた。彼は血の涙を流しながら、その命の続く限り、鬼と妖怪達を破壊した! もはや善界には何も残っていなかったのだ。
気がつくと雨はいつの間にか止んでいた。あまりにも恐ろしく、あまりにも深い胡蝶の悲しみに、僕は打ちのめされていた。
「じゃあ、お前の名前は蘭火と胡蝶と、二つあったのか?」
『そう』
「善界はそれからどうしたんだ?」
『鬼と・なった・善界は、その場にいた・敵たちを・全部・破壊した・あと、鬼芭王の・もとに・向かった』
「鬼芭王?」
『すべての・鬼たちを・つかさどる・破壊の・神』
「神だって? 善界はそれに立ち向かったのか?」
『さしもの・善界も・人間。鬼芭王に・破壊された』
「そうだったのか。それで善界の一族は滅びたのか」
『いや・かろうじて・生き残っている』
「ええっ?」
『死んだ・善界の・妻は・子供を・身籠もっていた。その子は・奇跡的に・産み落とされ・助けられたの』
「そうか、じゃあその子孫が生き残っているかも知れないな」
『ちゃんと・生きてるわ』
「何だって? 一体、どこにいるんだ?」
『あたしの・目の前に・いるわ』
「あっ」
一瞬、眩暈がした。その瞬間、全ての謎が解けたような気がした。なぜ、自分が妖怪達に追われるのか、そしてこの胡蝶がなぜ、自分を助けてくれるのか。
「僕が、善界の?」
後藤氏がなぜ、黙っていたのかやっと分った。
僕は無意識に震えていた。
「でも今までの善界の子孫は、妖怪や鬼に狙われなかったのか?」
『たとえ・子孫でも・強力な・力が・なければ・妖怪には・関係ないの。だけど・あなたには・充分に・それが・現れている』
「えっ? 僕にそんな能力があるって言うのか? 馬鹿な!」
『この・京都にいる・鬼や・妖怪達は・あなたが・ここを・訪れた・ときから・一斉に・活動を・始めたの。だから・あたしたちは・必死で・あなたを・探したわ』
「そうだったのか、それで」
『佐伯・光司』
「何だい?」
『善界の・子孫の・あなたに・託したい・ものが・あるの』
「託したいもの? 何だい?」
胡蝶は懐から小さな、刀のような物を取り出した。
「何だい? そりゃ」
『死ぬ間際・まで・善界が・使っていた・魔神の・武器よ』
「魔神の武器?」
『あなただったら・かならず・この武器を・使えるはずよ』
「どうやって使うんだ?」
『この刀の・封印を・はがすの。そして・左腕に・突き刺せば・この・武器は・あなたのものと・なるわ・ただし』
「但し?」
『これからの・ことを・よく考えて・ほしいの』
「なぜだい?」
『この・封印を・剥いだとたん・凄まじい・妖気が・発せられるわ。そうすると・多くの・妖怪や・鬼が・あなたを・殺しに・やってくる』
「この武器を狙ってか?」
『そう。だけど・この武器は・魔神の・武器。あの・鬼芭王さえも・封印・してしまった』
「封印だって? じゃあ、鬼芭王はまだどこかで生きているのか?」
『そうよ。善界が・自分の・命と・引き換えに・封印したわ』
「どこに?」
『それは・あたしにも・判らない。あたしも・あのたと・長い眠りに・ついたの』
「そうか、いずれは復活するのかな」
『必要な・条件が・揃えば』
「そうか、この封印を剥いだ途端、僕は鬼芭王と闘う運命になると言うんだな?」
『それだけじゃ・なく・多くの・妖怪をも・敵にしてしまう』
「鬼芭王って強いのか?」
『もしも・復活したら・今の・あたしたちでは・とても・勝てない。だけど・まりちゃんなら、もしかすると…』
「まりちゃん?」
僕は自分の頭を撫で撫でしたり、鼻をつまんで喜んでいたあのまりちゃんを思い出した。
「まさか! あの抱き人形が?」
『けた外れの・力を・感じるの。あたしが・妖怪に・追いつめられた・ときも・助けて・くれた』
「なるほど、それで超常現象調査会のメンバーになったのか」
『光司、よく考えて。それが・嫌だったら・すぐに・京都を・出て・普通の・暮らしに・戻ればいい。善界の・子孫であっても・あなたに・闘う・義務は・ないわ。あたしも・みんなも・強制は・したくない。これは・あなたが・自分で・決める・道だから』
胡蝶は自分の手に乗っている、小さな刀を握り絞めた。
「分った。暫く考えさせてくれないか、すぐに決められる事じゃないし」
『それがいい』
「それとさ」
『なに?』
「お前の名前、やっぱり胡蝶の方が似合ってると思うよ」
『ありがとう。光司』
胡蝶は微笑んだ。
「そうそう、今日は何でわざわざここに呼んだんだ?」
『ここは・善界が・いつも・夢の・練習に・来ていたの。善界は・夢の・名手だったわ』
「それでここを選んだのか。お前は、何のために鬼や妖怪を追うんだ?」
『雪ちゃんの・ためよ。ただ・それだけ』
「そうか。分ったよ、サンキュー!」
僕は本堂を後にしようとした。善界の事、先祖の事、魔神の武器の事、まりちゃん達の事、これからの事、あまりにも考える事が多すぎた。しかし、出口に向おうとした時、突然、異変が起こった。 ドゴオオンンン! と本堂の方で大爆発音がしたのだ!背後で爆風が走る。
「うわっ! 何だ?」
木の破片がバラバラ降ってくる。僕は急いで本堂に引き返した。
「胡蝶〜!」
一体、何が起こったのか? 本堂の所まで行くと、胡蝶と僕が話していた場所は跡形もなく破壊されていた。あちこちに観音像の破片や、四散した柱の破片が転がる。
「どうなっちまったんだ、 胡蝶は?」
その時、本堂の方から大勢の騒ぐ声が聞こえた。
「待たんかいな! 何のつもりや!」
「それを返さんかい!」
見ると本堂の中から、人影が飛び出してきた。それを何人かの若い僧が追っている。
「返せちゅうとんのや! そやないと」
数人の若い僧達は長い棒を降りかざした。背の高い男はそれを見てニヤリと笑う。
「ほう、どうすると言うんだ?」
「こうしたる!」
一斉に棒を持った僧達は、背の高い男に襲いかかった。だが、男はそれらの攻撃をいとも簡単にかわすと反撃に出た。
「まだまだ青いな」
男の目にも止らぬ攻撃が始る。一体、どんな技なのか? 佐伯にはそれが何なのか見極める事ができなかった。あまりに男の動きは早すぎるのだ。ほんの数秒で、数人の若い僧達は砂利の上に転がっていた。男は容赦なしに倒れている男の腹部に蹴りを入れる。
「グワッ!」
「ほらどうした? さっさと立てよ!」
男は尚も若い僧に蹴りを入れ続ける。まるで僧をもて遊んでいるかのように、その顔は残虐な喜びに満ちていた。
「たったこれくらいの物に執着しやがって。愚かな奴らだ」
そう言う男の手には、小さな真っ白な容器が握られていた。僕はとうとう我慢ができなくなって、男の前に歩み出た。
「おい! 待てよ!」
「何だ、お前は?」
「もう、勝負はついているだろう? いい加減にしたらどうなんだ!」
「いい加減に? それもそうだな。そろそろ止めを刺すか!」
男はそう言うと、大きく足を降り上げて、一気に目の前にいる僧を蹴り上げた。
「うっ!」
と呻き声を上げて、僧は宙に舞い上がり、そのまま体を歪めて砂利の上に転がった。
僧の目は、開かれたままになっていた。
「わあああ! しっかりせんかい!」
他の僧が、地面に転がった僧に駆け寄る。続いて僧達の号泣が聞こえてきた。
「この野郎! 人を何だと思ってやがるんだ! 虫ケラみたいに殺しやがって!」
怒りに我を忘れると、死んだ僧の長い棒を拾った。
「…ほお、小僧! ワシとやるつもりか? お前も死にたいようだな!」
言うが早いか、男の攻撃が始った! 凄じい連続攻撃に手も足も出ない。
ドガア! という音が響きわたり、男の拳が本堂の柱に食い込む! 改めて恐怖を感じた。
「お次だ!」
男の強烈な蹴りで木でできた彫刻も、あっという間に真っ二つになる。こいつは人間なのか?
「柱をあんなに殴っても平気なんて!」
今度は男の蹴りが飛んでくる! 風切り音だけでも、空気がビリビリと震えた。髪の毛が宙に舞う。
「クソッ!」
負けじと長い棒を横に振る! その棒が男の横腹にヒットした。
「やった!」
「馬鹿め!」
男はそう言うと脇腹にある棒を一気にへし折った。両手にあまる程のこん棒が、簡単に折れてしまう。
「貰ったぞ!」
男は素速く僕の懐に入り込むと、強烈な蹴りを腹に叩き込んだ!
ドゴオオオ! という音が全身を貫く。
「グオッ!」
僕は一瞬の内に宙を飛んでいた。そのまま、厚い本堂の壁を突き破り、障子やガラス戸までも突き破って、砂利の地面の上を十メートルくらい滑ってゆき、巨大な木の根元にモロに体を打ちつけた。
「あ、ぐっ!」
呼吸ができない? 腹を押さえてのたうち回った。あばら骨が何本も折れているようだ。
「うぐっ!」
駄目だ! 息ができない。自分はこのまま死ぬのか? 口からも泡と一緒に大量の血が流れ出始めた。
「ふん、口ほどにもない奴だ!」
見上げると、男は目の前に立っていた。とどめを刺そうとして、その足を振り上げる!
僕は無意識に、手元に落ちていた石を投げつけていた! それが男の顔面にブチ当たる。
「ぐっ! これは面白い! 楽しくなってきたぞ!」
男は鼻血を拭うと、ニタリとしてその表情を歪めた。
「ただ殺すつもりだったが、気が変わった。なぶり殺しにしてやろう!」
「くそ…負けるもんか」
僕は最後の力をふり絞って何とか立ち上がったが、足下がフラついていた。さっきの強烈な蹴りが足にきていたのだ。だんだんと視界もボヤけてくる。男は僕の首を鷲掴みにした。
「まずはきさまの、目を潰してやろう!」
男が僕の目に指を食い込ませようとした。しかし次の瞬間、不意にその力を緩める。
「まさか?!」
ズバアアアアアアアアア! という音と共に、凄じい衝撃波が男の顔面に叩き込まれた! 悲鳴を上げて男は後ろへ飛んだ!
『おのれ! やっぱり生きていたか!』
男の顔はもはや、人間の顔ではなくなっていた。その表情は凶悪な鬼と化しつつある。
体中のあちこちの皮膚が焼けただれ、やがて狂気を帯びた鬼の顔と、人間ばなれした筋肉質の体が姿を現した。
「あれくらいで滅ぶはずもなかったか、蘭火!」
『今度は・あたしが・相手よ! 疾鬼!』
胡蝶は僕の後頭部から飛び上がると、本堂の屋根に舞い降りた。
『一体、どこに隠れているかと思ったら、こんな所に結界を張って潜んでいたとはな! 考えたな、蘭火!』
『舎利を・どこに・やったの!?』
『ケケケ! 今はお前に構っている暇はない! もうすぐ鬼芭王様の復活だ! その時がきさまらの最後だ!』
『そうは・させないわ!』
クワアアアアアア! と激しい音と共に、胡蝶の右手から衝撃波が走る。地面の砂利が土煙を上げて吹き飛んだ。疾鬼は身を翻すと、本堂の屋根に飛び移る。
『死ね! 裏切者め!』
ボオオオオオオオオ! と疾鬼の口からは猛烈な炎が飛び出し、本堂の瓦が炎と共に吹き飛ぶ。僕はおぼろげな意識の中で胡蝶と疾鬼の闘いを見ていた。
「こ、胡蝶」
胡蝶と疾鬼は地面に飛び降りた。互いに百二十メートルはある本堂の両端に移動して向い合う。
『蘭火め! 破壊してやる!』
疾鬼は胡蝶の方に向って両手をかざした。球状のエネルギーが一気に膨れ上がり、それが胡蝶の方に向う。
『鬼雷獣! 召喚!』
胡蝶も両手を疾鬼の方に向けて、鬼雷獣を呼び出した。
ズバアアアアア! という音が頭上に響く! 両者から発射されたエネルギーが本堂の中央でブチ当たり、辺りは真っ白な光に包まれた。一瞬にして本堂は炎に包まれ始めた。物凄い爆発が起こり、両者は吹き飛ぶ。
『グオッ! 相打ちか! 勝負はおあずけだ!』
『待てー!』
疾鬼は信じられないスピードで飛び去っていった。それを追いかけようとした胡蝶はハッとして、僕の方に戻ってきた。
『光司! 大丈夫?』
「体がバラバラになりそうだ」
『しっかりして!』
何とか立ち上がる。
「そこまでや! 放火魔!」
「観念しいや!」
気がつくと周囲は警官隊に囲まれていた。全員、手に銃を持っている。本堂が炎上したので、誰かが通報したらしい。
「クソッ、このままじゃ…」
その時、突然周囲の景色がボンヤリと霞んできた。地面の色が、燃え上がる炎の色が、白くなっていく。と同時に、全身が軽くなっていく。
「一体、どうしたんだ?」
僕はそのまま気を失ってしまった。気がつくとどこかの座敷で寝かされていた。ボンヤリと目を開けると部屋の天井と一緒に、胡蝶とまりちゃんの姿が目に入った。
「僕は生きていたのか?」
『気がついた? 光司』
『良かった。もう大丈夫ね!』
まりちゃんが僕の目の前に立ち上がって言う。
「あれから、僕はどうなったんだ?」
「まりちゃんにテレポートして貰ったんですよ」
声のする方に顔を向けると、後藤氏が立っていた。ハンカチで汗を拭きながら、何やらごそごそやっている。
「テレポート?」
「ええ、私とまりちゃんが三十三間堂に行った時には、既に本堂は炎で焼け落ち始めていましたからね。周りには警官隊もいたし、仕方ないので、その場でテレポートさせたんですよ」
「あそこまで来ていたんですか? だったら助けてくれたら良かったのに」
「いや、それがですね。あなたが危ないと分ってから、あそこに移動したんですよ。何せ仕事が忙しかったもので。気にはなっていたんですが、すみませんね。仕事もしないと超常現象調査会は運営していけないんです」
「ところでここはどこですか?」
「大原の三千院の離れですよ。佐伯さん」
「三千院? どうしてまた?」
「ここの門跡さんは私の旧い知合いでしてね。ここには超常現象調査会の秘密のアジトを置かせていただいているのです。恐れ多くも門跡寺院(皇族が住持する寺)にそんなものがあるとは誰も思いませんからね。それと今日はここに、この間のメンバーが集る事になっています」
「この間のメンバーって、あの二人の刑事ですか?」
「そうです」
「何でまた、こんな所に集る必要があるの?」
後藤氏は振り返るとニコッとして言う。
「今日はですね、ここで湯豆腐を食べる事になっています」
「湯豆腐? 何なんですか? 一体」
「理由は後々説明しますけどね、これが我が会の方針なんです」
「後藤さんは何でも、説明が後になるんですね」
「はははは! 私は貴方が身をもって体験した後に、説明をした方が貴方の納得がいくと思っているだけですよ。体験した事はどんな説明よりも雄弁だ」
「ははあ」
「ところでケガの具合はいかがですか?」
「ええ、そういえば痛みも、あれっ? 僕は確かあの男に腹を蹴られて」
「そう。アバラが八本も折れていました」
「どうして痛まないんだ?」
『あの・武器の・力を・少しだけ・使ったの』
胡蝶が言う。
「例の封印つきの武器か。あれでケガが治ったりするのか?」
『ある程度・なら。少し・時間が・かかるけど』
「でも、腹に痛みはないし、やけに早いじゃないか」
腹部をさすりながら言った。
『だって、光司が気絶してからもう、丸二日経ってるのよ』
まりちゃんが、僕の腹の上で飛び跳ねる。
「二日も? その間、ずっと僕は寝ていたのか?」
「ええ、グッスリ寝ていましたよ。八橋おいしい、とか言いながら」
「そ、そうですか。ところで胡蝶」
『なに?』
「僕を蹴ったあの男は人間なのか?」
『あれは・人間に・かたちを・替えた・「疾鬼」という・鬼』
「鬼芭王みたいなものか?」
『鬼芭王・ほど・強くないわ。疾鬼は・鬼芭王の・手下なの』
「そうか、まるで歯が立たなかったな。呼吸ができない時は、死ぬかと思ったよ。それより胡蝶、疾鬼はどうして三十三間堂にいたんだ?」
胡蝶はその場に正座すると答えた。
『疾鬼は・京都中に・飛び散った・善界の・「舎利」を・狙って・いるの』
「舎利を? どうして?」
『「舎利」・つまり・善界の・骨には・強力な・「妖力」が・込められているの。鬼芭王の・復活には・絶対に・それが・必要なの』
「…」
『鬼芭王は・地面の・奥深くに・封印・されているの。その・封印を・吹き飛ばすには・強力な・破壊力をもつ・妖力が・必要』
「なるほど、それで疾鬼は京都中を飛び歩いているってわけか。舎利がどこにあるか特定できないのか?」
『判らない。それには・疾鬼の・出現を・待つしかない。疾鬼も・必死になって・舎利を・探している・はずだから』
「疾鬼がどこに現れても、すぐに分るようにセンサーを張りめぐらす必要があります」
後藤氏が頷きながら言う。
「やあ、どうも。遅れました」
やがて、田村刑事と平田刑事が入ってきた。二人は両手に大きな包みを抱えている。
「お二人共、何ですか? その包みは」
「これは今日の、豆腐料理の材料です。高級豆腐に、シイタケに鴨の肉。ネギにシラタキ、エノキダケ、それにダシを取る羅臼コンブ! おっと、これを忘れてはいけない! 泡盛に大吟醸酒だあ!」
「これは素晴らしい!」
後藤氏は顔をほころばせて喜ぶ。この連中は何を考えているんだ? こんな非常時に豆腐料理なんて。イマイチこの連中のキャラクターが掴めない。
「さあ! では早速、宴会モードに入りましょう」
後藤氏がそう言うと、田村刑事と平田刑事は僕が寝ている蒲団をひっくり返した。
途端に僕は畳の上にゴロゴロと転がった。
「な、何するんですか!」
「ささ、佐伯さんも宴会の準備を!」
無理やり着替えを済ますと、連中が鍋に材料を入れるのを手伝った。やがて鍋からはグツグツという音に交じって、食欲をそそる匂いが漂ってくる。
「では皆さん、乾杯といきましょう!」
「かんぱ〜い!」
一同は一斉に食事を始めた。釈然としない僕の気持ちをよそに食事のシーンは進行していった。
ますます訳が分らなくなる。
「あの、皆さん」
「うん、この鴨の肉は最高です!」
「後藤さん?」
「田村君、そのカイジャクシ、取って下さい」
「はい」
「あの、後藤さん!」
「この鍋の材料が尽きたら、ダシは残してウドンを入れましょうかね」
「御飯を入れて、ぞうすいにしてもいいですよ」
「後藤さん!」
「まりちゃん、胡蝶、おいしいかい?」
『うん、おいしい!』
『おいしい!』
「後藤さあああんんんんん!」
僕は大声で叫ぶとお膳をバン! と叩いた。一同は不思議そうな顔で僕の方を見た。
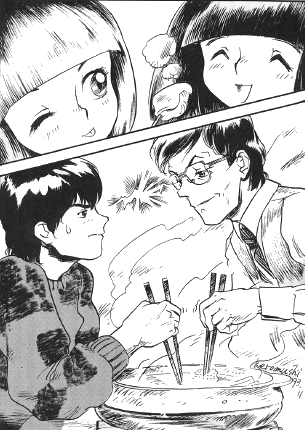 「どうしました? 佐伯さん。おいしくないですか?」
「どうしました? 佐伯さん。おいしくないですか?」
「料理の話をしている場合ですか! 一体これは何の真似です?」
「何って、ただ食事をしているだけです」
「今日は超常現象調査会の集会でしょう? 肝心な話はいつするんですか!」
「だからこれが集会ですよ。そうそう明日はこの三千院を散策して嵐山に向いますよ」
「はあ? だって、飯食って酒飲んで、遊んでいるだけじゃないですか」
「佐伯さん、とにかく食べなさい。食べないと体の方も治りませんよ。鬼や妖怪と闘うにはまず、その基本である体を大事にしないと」
「それはそうですが、何かちょっと緊迫感に欠けるんですよね」
「我々がこうして食事をするのは、当たり前の事ですよ。映画や漫画のどんな凄いヒーロー達でも本当は必ず食事をしている筈です。トイレにも行き、風呂に入ったり、酒も飲んだりする筈です。そうでしょう?」
「そ、それはそうですが」
「心配しなくても、佐伯さんの知りたい事は後で説明しますよ。とにかく今は食べないといけません。これは貴方に課せられた使命です」
「はあ、分りました」
強引のような、筋が通っているような説明を受けて唖然としたが、まずは食べる事にした。食事を取るのが使命? 何だかピンと来ない。僕は頭では、映画やTVの場面のような、もっと深刻な状況を考えつつも、鍋の中に鴨の肉を探した。箸でつつき回していると、肉らしきものを発見し取ろうとしたが、そこで田村刑事の箸と衝突した。田村刑事と僕は睨み合った。互いの動きを心の中で探ろうとする。
「田村さん、悪いけどこの鴨の肉は僕のですよ」
「ふ〜ん。おもろい事言うなあ」
田村刑事は関西の出身なのか? 本気になると関西弁が出てくるようだ。
二人は気合いを込めて瞬間の勝負に出た! だが、鍋の中に鴨の肉は見当たらない。
「どこだ? どこに行った?」
『へっへ !』
気がつくと鴨の肉は、まりちゃんと胡蝶の手に渡っていた。
『残念でした!』
「くっそー!」
食事が終わった後、超常現象調査会はようやく本題に入ろうとしていた。酔い覚ましのコーヒーを飲みながら、再びテーブルを囲む。
「この会っていつもこんなノリですか」
「そうですよ」
そう言いながら後藤氏は一枚の写真を僕の目の前に差し出した。手に取って見ると色あせた写真には、何かの学者だろうか? 一人の白衣を着た男が写っていた。
「これは、誰ですか?」
「私の古い友人です」
「この人が何か?」
「彼は、谷山先生といってですね。昔からある分野の研究を専門にやっていた教授です」
「何の研究をですか?」
「鬼や妖怪の研究です。超常現象調査会の創設者でもあります」
「この人が創設者。で、今はどこにいるんですか?」
「彼は八年前に亡くなりました。あの疾鬼にやられてね」
「!」
「谷山先生は昔から、この京都を拠点に研究を続けていました。ところがある日、彼は偶然、嵐山の土中から一つの舎利を発見したのです」
「それが善界の骨だった」
「お察っしのとおりです。その舎利はけっして開かない真っ白な容器に入っていて、普通の寺なんかに納められている舎利とは、あまりにも違っていた。彼は早速、私の所へやって来ましたよ。凄い大発見だと言ってね。彼は興奮していました」
「それで、どうしたのですか?」
「私もその頃は、商売に明け暮れていましたからね、正直いって何がすごい発見なのか分らなかったのです。まあ彼は学生時代からの親友ですからね。論文が完成したら、私が骨を折ってちゃんとした本にしてやろうという事くらいは考えていましたが」
「…」
「当時、彼の超常現象調査会については私も今の佐伯さんと同じように何をやっている会なのか正体不明でしたからね。自分には直接関係ないと思っていました」
「谷山先生はどこで疾鬼にやられたのですか?」
「同じ嵐山でです。彼は嵐山にまだ舎利がある筈だと信じていましたから。再び調査に取りかかった矢先でした」
「警察では、月の輪熊にやられた死亡事故として処理しただけなんですよ。府警の過去の資料を見て分りました」
田村刑事がタバコをくわえながらそう言った。
「私もですね、谷山君はおそらく、仏教史上の新発見をして夢中になっているのだろうくらいに考えていました。ところが事態はそんな生易しいことではなかった。くやしい事に私にはそれが彼の死後にやっと分ったのです」
後藤氏はそう言いながら、さらに一通の封書を差し出した。これも色あせていて、あちこちに染みがある。
「手紙ですか?」
「谷山先生が死ぬ前の晩に書いて、ポストに入れたものです」
ゆっくりとその手紙を開いた。手紙は見事な筆跡で、長々と書かれていた。
しかし所々、その字が震えているのが分る。
「親愛なる後藤君へ」
後藤君、この手紙を君が読む頃には、私はおそらくこの世にはいないと思う。
突然だが驚かないで貰いたい。私は自殺する訳ではない。今となってはこうなる事は運命だったと、静かな気持ちで受け止めている。この間、君に夢中になって聞かせたあの「舎利」の話しだが、とんでもない物だったのだ。いや、これは歴史学者にとっては名誉な事かも知れないが。
あの舎利は大昔の仏舎利かと思ったら、実はそう遠い昔の物ではない事が分った。むしろあの舎利の価値は別の所にあったのだ。あの舎利を分析しようとして、私は色んな方法を試みてみたが、全て徒労に終わってしまった。とにかくあの容器は何でできているのか、金属で叩いても、レーザーや超音波をあててもビクともしない。X線で中を見ようとしても、無駄だった。もしもあの物体が人類にとって未知なる物だとしたら、これは世界的な大発見だ。君は笑うかも知れないが「宇宙からの物体」という事も考えた。
結局、現代科学ではラチがあかないので、私は宗教史上の観点からそれを再び調べる事にした。しかし東西南北、我が国のいずれの大学や図書館の資料にもそれは記載されていなかった。普通の学者ならここであれに、適当な説明文をつけて「歴史上の未知の舎利」として発表するだろうが、私はそうはしなかった。もしもあれがただの舎利だったら、あそこまで頑丈に中身を守る必要はない。もっとすごい秘密が隠されている筈だ。もしかしたら、あれは一般の仏教とは無関係なのではないか? 私はそう思った。となれば、あの中に入っているのは、ただの仏舎利ではないという事になる。同時に私はあの舎利は複数あって嵐山の他のどこかにも存在しているとの推論を立てた。
すっかり途方に暮れた私はさらに研究角度を変えて、今度は所謂「秘教」の文献にあたってみる事にした。その昔、日本に海外から色んな宗教が入り始めた頃、魔的な邪教も数多く入ってきた。その教義があまりにも危険であったために仏教界ではこれを御法度として厳しく禁じてきた。だからそれに関する文献は極端に少ない。
皮肉な事に私はそれらの文献を全て海外で発見した。明治維新の時に廃仏毀釈のドサクサで流失したものだ。その中の一つの本にあの舎利の事が書かれていた。その本によればああいう舎利は、凄じい妖力を持った者が死んだ時に形成され、他者が復活する時の再生用に使われるという。さらにその本とは別に、不思議な日本の秘教史の写本を手に入れた。驚くべき事に、それには我が国における秘教の歴史が手書きのサンスクリットで克明に書かれていたのだ。私は来る日も来る日も、夢中になってそれを解読した。その内容はまさに悪夢のような物語だった。
その内容の全てを今ここに、書く事はできないが、少なくともあの舎利が形成された理由が分ってきた。記述をよくよく調べて見ると、まずその秘教の史書のところどころには破壊的な「鬼芭王」という魔王の存在が記されてあった。その魔王は遠い昔に秘教の流入と一緒に海外から日本に移り住んだらしい。また驚いた事には日本にも秘教の術の使い手がいたようだ。その人物の名前は善界という。奇妙な事にこの善界は仏教史の方にも、同時代に登場しているのだ。
おそらく善界は仏法の僧だったが、鬼芭王の存在に気づいて、これに対抗すべく秘教に近づき、そのおそるべき力を手に入れたのではないか? 件の本の記述によれば善界は鬼や妖怪達と凄じい戦闘を繰り返している。だがこの善界の名はある時を境に急に消えてしまう。これは善界が戦いで死んだ事を表わすのではないか? 同時に鬼芭王の名前も徐々に出てこなくなる。鬼芭王は倒されたのか? それともどこかに封印されているのか?
私の推論はこうだ。おそらく善界は鬼芭王と戦って死んだ後に、その遺骨はなんらかの力であの舎利に形を変えられたのだ。もしその舎利達を元どおりに集める事ができたら、凄じい力を発揮するのではないだろうか? そして、もしそれを封印され今も生きている鬼芭王が自分の復活のために狙っているとしたら…。あまりに荒唐無稽と君は笑うかも知れない。
しかし私がそう考える根拠は、もう一つある。ここ二、三日、どこかで私の命を狙っている者がいるのだ。私は何度かそいつに殺されかけた。そいつはどうやら人間ではなさそうだ。おそらく私はそいつに殺されるだろう。だが私が死よりも恐れているのは鬼芭王の復活だ。記述にあったような激しい、身の毛もよだつような、そして決して表の歴史にその姿を現すことのない惨劇が繰り返されるのか? ともあれ、もう一つの謎はこの史書の原本を書いたのは誰かという事だ。なぜこのような裏の歴史を克明に書き続ける事ができたのか。秘教の渦中にあって何代にも渡りその歴史を見つめている者が存在するに違いない。
もちろん普通の学者がこの写本を見ても、でっちあげの絵空事と考えるだろう。だから学会でありのままを発表しても学者生命を失い、精神病院にでも入院させられるのがオチだ。だからこそ後藤君、君にだけは全て話しておきたかったのだ。この手紙の内容を信じようと、信じまいと、それは君の自由だ。
しかしこれだけは言っておきたい。鬼芭王はこの京都のどこかに潜んでいる。そしてこのまま推移せんか、近い内に必ず復活する。そうなっては遅い。これは日本人だけでなく全人類をも滅亡に導く事かも知れない。もしもできる事なら、君の力で鬼芭王復活を阻止して貰いたい。私の今までの研究データーや資料は全て家に置いてある。場所は君もご存知のとおりだ。
これから私はこの舎利を持って、嵐山に行こうと思う。まだ嵐山にはきっと何かがある筈だ。これは私の歴史学者としての戦いだ。最後に後藤君、今まで色々と世話になった事に感謝したい。世間にけっして認められない孤独な学者人生だったが悪くない一生だったと思っている。これも全て君との交友のおかげだ。
最後に一言、「ありがとう」をいわせて欲しい。
永遠に変わらぬ友情と敬意をここに。
一九八五年二月七日
谷山晃一 拝
僕はしばらくショックで何も言えなかった。
「こ、これが、真実だとしたら大変だ」
やっとそれだけ呻いた。
「そうです」
「じゃあ、谷山先生を殺したのはやっぱり」
「疾鬼でしょう。奴は谷山君が舎利を持って、再び嵐山を訪れる事に気づいていたのだ」
「何てこった」
僕は眉間に手をあてて暫くうなだれていた。
胡蝶が寄り添って言う。
『まりちゃんたちと・あたしは・それぞれ・別な方向から・疾鬼を・追っていたの』
「なるほど、最終的には胡蝶もまりちゃんも嵐山に目をつけた訳か」
『そこで・あたしと・まりちゃんは・出逢った』
『あたしと同じ生き人形さんだったから、嬉しかったわ!』
まりちゃんが胡蝶の両手を握り絞めて飛び跳ねる。
後藤氏はコーヒーのお代わりをいれながら、僕に言った。
「そういう訳です、佐伯さん。とにかく明日は嵐山にいってみたいと思いますが、如何ですか?」
「勿論、一緒に行きます。ところで後藤さんはその手紙を読まれた後、どうされました?」
後藤氏は顔をわずかに上に向けると、ため息をついた。
「さすがの私もどうしたらいいか分らなかったです。鬼芭王退治のために自分の人生を捨てる訳にはいきませんしね。そうしたら困る人が大勢出てきます。だから今の生活を維持しつつ、谷山君の遺志をついでいくしかない。そう思いました。私だって生身の人間ですからね。映画のヒーローのような訳にはゆきません。」
「なるほど、だから超常現象調査会はこんな感じになったのですか」
「そうです。いろんな人間が集って、現在の自分の立場でできる事を探す! これが私のやり方です。文字どおりそれしかできない訳ですからね。だから佐伯さんも、もし入会されたら、好きにやって下さい。それぞれが自分の研究テーマを見つけて、好きにやればいい。私は強制や命令は嫌いだし、それじゃ本当は人がついて来ない事を、商いで学びましたからね」
「好きに、ですか?」
「寝ててもいいし遊んでてもいいですよ。闘いから逃げても構いません。好きな時に会に入って、好きな時に辞めてもいい」
田村刑事がコーヒーを飲み干して言う。
「来るものは拒まず、去る者は追わず、これが後藤さんのやり方です。だから我々は今までやってこれた。そうそう! 明日は面白い連中に会わせましょう!」
「こういった事は、一朝一夕で解決できる問題じゃないですからね。のんびり構えてやることですよ。我々の代でできなかったら、誰かが我々の意思をついでゆくでしょう。」
連中の言葉に、僕は一種の深い感動のようなものを味わっていた。世間一般ではなかなか見られない真の自由を、この連中の生きかたに見たような気がしたのだ。
「まりちゃんと後藤さんは、いつ出会ったんですか?」
『十年前よ!』
「ある天才人形作家からゆずり受けたんです。どうしてまりちゃんが生きているのかは、後藤屋で説明しましたよね?」
「はい。まだよく分らない所もありますが」
「さて、夜も更けてきたし今日はここで寝るとしましょう」
一斉に蒲団を敷き、電気を消して寝床に入った。心の中で考える。
僕は、どうしたらいいんだろう?
|
|