突然、腹の上でドスン!という音がした。一体、何が腹の上に乗ったのか。
僕はボンヤリとした頭で、おそらく胡蝶のイタズラだろうと思った。
僕はわざと目をつぶったままで不機嫌そうに言った。
「胡蝶、僕はまだ眠いんだ。悪ふざけするなよ」
そう呟いてみたが、腹の上に乗っているはずの胡蝶からは、何の返事もない。よく考えて見れば、その重さはとても人形の胡蝶のものとは思えなかった。
「一体、誰だ?まさか田村さんじゃないだろうな…」
そう思って、ゆっくりと起き上がった時、一瞬、言葉につまった。腹の上に乗っているのは胡蝶でも田村刑事でもなく、見たこともない子供だったのだ。
「誰だ?」
隣に目をやると、胡蝶は枕元で寝言を言っている。
目の前で寝ている子は、微かな寝息をたてていた。幼い女の子だ。色の白い浴衣を着ており、小さな下駄もそばに転がっていた。うつぶせなので、肩まである髪で顔は見えない。
こんな時、どうしたらいいのだろう?ホテルのフロント係を呼べばいいのか?この子はどこから入ったんだ?朦朧とした頭では全く分らなかった。
「どうしよう、この子は何なんだ?」
そう思っていた時、傍らに寝ていた胡蝶が目を覚ました。
『光司・おはよう』
そう呟くと、胡蝶は暫くボンヤリとしていたが、その見知らぬ子に気がつき、じっと怪訝そうに女の子を見つめている。
『誰?・この娘?』
僕が途方に暮れていると、部屋の呼び出しホーンが鳴った。
「はい、どうぞ」
後藤氏がまりちゃんを連れて、部屋の中に入ってきた。
「どうしたんです?あんまり遅いから迎えに来ましたよ」
『お早よう…ン?…!』
まりちゃんは後藤氏の耳元で何事か囁くと、ベッドの上で寝ている女の子を指さした。
一瞬、後藤氏は凍りついたような表情となり、深くため息をついた。
「あの、後藤さん?」
「佐伯さん。真面目な話、ロリコンは早いうちに終わらせときなさい。でないと後々まっとうな社会生活がおくれなくなりますよ」
「何、訳のわかんない事言ってるんですか、僕はロリコンじゃない!」
そう叫んだ時、みんなが部屋の中に入ってきた。
「お早ようございます。どうなさいました?」
「田村くん、林田さん、大変なんですよ」
今度は後藤氏がヒソヒソ声で事の次第を説明し、ベッドに寝ている女の子を指指した。
「あああ佐伯さん、何という事でしょう。それだけはしてはいけません!」
「違うって言ってるだろ!」
「佐伯さんって、やっぱり危ない人だったのね。あたしを見る目が怪しいと思ったわ」
玲子が眉をひそめて言った。
どうも全員、僕が女の子を連れ込んだと思ったらしい。
「誤解だよ、昨日あれだけ戦った後に、そんな気力がある訳ないでしょ?」
「まあまあ、佐伯さん。ムキになるなよ。我々はみんな君の味方だ」
「違うってば!」
僕がそう絶叫した時、後藤氏が急に冷めた口調で言った。
「さて、あんまり佐伯さんをからかうのも可哀そうだから、そろそろその女の子と話してみましょう」
「佐伯さん、その子を起こしてみて下さい」
言われるままに、うつぶせに寝ている子をゆすぶってみた。
やがて一同が見守る中、その子は目を覚ました。大きな両目をパッチリと開けると、その子は微笑んだ。
「お早ようございまちゅ」
「あ…?ああ、お早よう」
年の頃は五〜六歳ぐらいだろうか?
「君は、どこから来たんだい?」
「あっちでちゅ」
女の子は人差し指を天井に向けた。
「あっち?天井からこの部屋の中に入ったのかい?」
「違いまちゅ。もっと上でちゅ」
「上って、まさか空?」
「そーでちゅ。佐伯光司ちゃま」
「ええっ、僕の名前を知ってるのか?」
「もちろんでちゅ」
女の子はニコッとした。
「やっぱり佐伯さんが、さらってきたんだ」
林田が玲子に囁く。
「どーして、その方向に流れるんだよお!」
まりちゃんは後藤氏の腕から飛び降りると、その女の子のそばに寄った。
『お早よう』
「お早ようございまちゅ」
『お名前、何ていうの?』
「ことだまっていいまちゅ」
『それ、名字なの?名前?』
「どっちでもないでちゅ。ことだまだけでちゅ」
『どっちでもないって…』
ますます分らない。
「もしかしたら、愛称かも知れませんよ」
田村刑事が言った。
「まだ名前を知らないって訳ですかね?それとも親がそう呼んでるとか」
「一応、写真を撮って警察関係にバラまいてみましょう。その子の服装も遠出をするような感じではないしね。もしかしたら近くに住む子かも知れないし、捜索願いが出ているかも知れない」
田村刑事はそう言うと、コートのポケットから携帯カメラを取り出した。
「はい、ことだまちゃん。いい子でちゅね、チーズでちゅよ」
自分を「ことだま」と言った女の子は、クスクスと笑うと浴衣に巻いている帯をきちんと直し、ちゃっかりと、ポーズをとった。
「おませさんだなあ…」
後藤氏が笑う。
「どこかに預けるんですか?」
「いえ、このまま我々で保護しましょう。なぜか佐伯さんのことを知っているようだし。連れている内に遅かれ早かれ、何かが分るでしょう」
後藤氏の提案で、暫くこのことだまを連れて回る事になった。
いやはや、とんだ珍客である。
ことだまを連れてホテルを出ると、町中は大勢のヤジ馬と、それを追い回すパトカーでごったがえしていた。それも当然だ。昨日のうちに東大寺が大仏ごと消滅していたのだから。興福寺の時よりも大勢のマスコミ関係者が来ているようだった。
「田村さん、行かなくていいんですか?」
「実は、明け方から携帯電話が鳴りっぱなしでした。あんまり鳴りまくるから、切ってしまいました。いやぁ、華いでるなぁ」
「もしかして例の謎の阿修羅ツアーなんてもうできてるんですかね?」
「そんなのできたら応募者が定員を超えてしまって大騒動になりますよ。でも近いうちに実現するでしょうなぁ。旅行社は利にさといから。『謎の阿修羅饅頭』なんかが土産屋に並んだりしてね」
空を見上げると澄み切った秋空にうろこ雲が列をなしているのが見えた。
「まりちゃん、うろこ雲だよ」
『お魚がたくさん、泳いでいるみたいね。でもあれって、近くに寄ったら薄くなっちゃってつまんないのよ』
「まりちゃんは雲の近くまで行けるんでちゅか?」
『そうよ。お空を飛ぶのは大好き』
「ことだまも、雲の上に上がるのは好きでちゅ」
『?』
この子の言っている事はどこまでが本当なのだろうか?
奈良公園に近づくと、目の前をのんびりと渡っている鹿の姿が目に入った。
「ここの鹿達も何とか落ち着いたようですね」
「うん、鬼烏も一羽だけは退治したからね。ここの鹿は十月に入ると、角切りという行事があってね、牡鹿の角が危険だから切ってしまうんだ」
「何か勿体ないですね」
「角が伸びたままだと、観光客が危ないからね。それに牡鹿同士も頭突き合いをするから怪我をするだろ?」
「へえ」
ことだまは、下駄を引き摺りながら、頬を赤く染めて走り回っている。
やっぱり変だ…。そろそろ親の名を呼んで泣き出すかと思っていたのに。
目の前にしゃがみこんで聞いてみた。
「なあ、お前、本当はどこから来たんだ?」
しかし、相変わらず彼女はニコニコとして、空を指差すばかりだった。
「お空でちゅ!」
「そうでちゅか。分りまちた」
だんだんこっちまで幼児言葉になる。
目の前に広がる、春日大社の景色は平和そのものだった。大きな社殿の朱色の柱からは釣灯篭が見られ、この参道から南に広がる飛火野に鹿達が悠々と通り過ぎていく姿が見える。たくさんの杉木立が風でざわめき、その風が頭上ををすり抜けていく。
のんびり石の上に座っていても、心の中には色んな心配が沸き上がってきた。そう、昨夜の事だ。
「威追(いお)っていったよな」
何となく呟いてみる。あの恐るべき力を持った魔性の男、阿修羅の手先なのか?
そして、まりちゃんとよく似たブラックマリー、あの人形の正体は?何のために生み出され、なぜ僕たちに敵対するのか。
そして阿修羅の最終的な目的は何なのか?
僕たちは彼らから日本を守ることができるのか?
「何を考えているの?」
気が付くと、長い髪とスラリと伸びた両足が目に入った。玲子だった。
「やあ、なんだい?」
「佐伯さんたら、さっきからずっと考え事をしてるんだもの。皆なもう、行っちゃったわよ。早く行きましょう」
だいぶ僕たちに馴れてきたのか、彼女の言葉使いも変わってきた。今日の玲子はいつもの袴姿ではなく、セーターの下に藍色の長いパンツをはいていた。袴の時とはまた違う美しさがあった。一瞬、兄の林田が羨ましく思えた。
「今度はみんなどこに行くんだい?」
「えーと、確か」
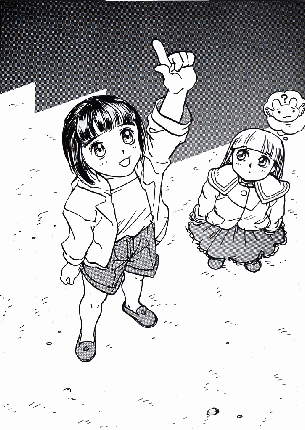 玲子がそう言いかけた時、突然、立ち止まった。みるみるその表情が緊張でこわばっていく。いきなり時間が止ったようだった。
玲子がそう言いかけた時、突然、立ち止まった。みるみるその表情が緊張でこわばっていく。いきなり時間が止ったようだった。
「どうした?」
「しっ、黙って!誰かいるわ」
「!」
咄嗟に周囲を見回したが、誰もいなかった。
「気のせいじゃないのか?」
「いいえ、確かに感じる。巨大な力が二つ、いえ、三つ!」
玲子はそう言うと、近くに立っている石の灯篭に近寄った。
「その石灯篭がどうかしたのかい?」
「この辺の気が乱れているわ。亜空間かも知れない」
「まさか!」
突然、玲子に手を引っ張られた。
「中に入ってみるわ。何かあったら戦ってね!」
「ええっ?亜空間の中に?」
玲子がその灯篭に手を触れて、何事か呪文を唱えた途端、目の前の景色がグニャリと歪んだ。視界が真っ白になり、意識が遠退いて行った。
「…」
「佐伯さん、起きて…佐伯さん!」
「ん、もう着いたのかい?ここはどこ?」
「さっき言った亜空間の中よ。ここは私たちの世界とは違うから気をつけて」
周囲を見渡してみると、辺りは濃い霧に覆われていた。どっちがどっちの方向なのか見当もつかない。所々、霧の中から黒い大木が真っ黒な空に向かって突き出しているのが見え、その木の枝には見た事もないような不気味な丸い物体がついていた。それは木の実ではなく巨大な眼球だった。その上には稲妻のような形をした血管のようなものが走り、この大木が何等かの生き物である事が分った。
「うへえ。何て気味の悪いところだ。早く帰りたいよ」
「そう言わないで、暫く進みましょ」
玲子はそう言うと、黙って僕の腕を取った。一瞬、ドキッとしたが平静を装った。
でも、何か変だ。心の中に嫌な予感が広がった。
「何かいるのかな?ここはどうやったら出られるんだ?」
「どうして出る事ばかり考えるの?私と一緒じゃ嫌?」
「えっ?」
玲子はいきなり、両手を首に回してきた。黒い大きな瞳がぐっと近づく。
「玲子さん?うわあ!」
突然の変化だった。見る見るうちに玲子の顔は溶けてただれていき、そのまま肉塊となって地面に落ちた。体の他の部分もいっせいに溶けだし、ズルズルと下に向って流れていく。アメーバーのようになった不気味な液体人間が、体にまとわりついてくる。
「クククク、あなたを離さないわぁぁ」
その不定形のアメーバーには醜い女の顔がついており、耳元まで裂けた口からは、ちろちろと蛇のような真っ赤な舌が出ていた。大きく口を開け、おぞましい顔が近づいてくる。
落ち着くんだ!
自分にそう言い聞かせ、ベルトの辺りをまさぐった。そして腰にさしていた短刀を引き抜いて、アメーバー女の顔面に突き立てた!
「ギャアア!」
悲鳴を上げるアメーバー女に、僕は何度も何度も夢中で短刀を突き刺した。その度に緑色の体液が飛び、それが全身にふりかかった。
「な、なぜそんな武器を、ただの刀ではないなあ!」
「林田さんから貰った、霊力の込められた御神刀だ、くらえ!」
そう叫ぶと僕は、化け物を上から下へ一気に切り裂いた!切り裂かれて半分になった女の体が足下にのたうち回る。
やがて、闇の中に溶け込むように化け物の姿は消えて行った。全身にかかっていた返り血も同時に消えていった。
「変だ、あまりにもあっけなさ過ぎる」
そう思って額の汗を拭いた時、別の方向の闇に誰かが潜んでいるのが分った。
「誰だ!」
『幻と戦った感想はどうだ?佐伯よ』
「何!」
頭上の闇の中から、不気味な魔人の顔が浮かび上がった。威追だった。黒いマントを風に翻しながら、こちらを見下ろし、薄笑いを浮かべている。
「生きていたのか」
『ククク、どうやら幻にだけは勝てるようだな』
威追が手を伸ばすと、暗黒の中に赤い光が灯った。
『あの時は危なかったが、寸でのところで脱出したという訳だ』
『あたし達にもテレポート能力があるのよ』
威追の隣に、ブラックマリーの姿も闇の中から浮かび上がった。
「ちくしょう!」
『佐伯よ、観念するがいい。お前達全員が集った時は不思議と強い。だが、一人一人ではどうかな?』
威追がニタリと笑う。もう、昨日の傷も治癒してしまったのか?亜空間では連中の方が圧倒的に有利なようだ。
「各個撃破するつもりかよ。きたないぞ」
『それが戦略の基本だ。負けるような戦いはするだけ無駄ではないか?昨日の腕の傷のお礼はここでしてやろう。ククク』
「くそっ、善界の弓よ、出て来い!」
そう叫んで左手を宙にかざした。だが、なぜか左腕からは何の反応もない。いつもなら真っ先に飛び出してくるはずの光の渦が出てこないのだ。
「善界の弓よ、出てこい!」
再び叫んだが、弓は沈黙したままだった。
『馬鹿な奴め。ここがどこなのか、まだ分ってないようだな』
威追が顔を歪めて嘲笑した。
「どういう事だ!」
『ここは我々の発生させた亜空間、つまりこの空間の中だけなら、どんな事でも我々の思いのままだ。きさまの魔人の弓も出てはこれぬ。何を召喚しようとも、すぐに打ち消されてしまうのだからな』
「そんな馬鹿な!」
威追は瞬時に僕の前に移動し、攻撃してきた。次々に魔人の長剣が襲いかかる。背中、次は右手、次には左足に剣が刺さり、腹部にも傷が走った。
「ぐぅ」
倒れながらも短刀を掴もうとする手を、威追の足が踏みにじる。指の骨の折れる音が闇の中に響いた。
「ぐわあ!」
「ククク、佐伯よ。もっと苦しめ、苦しんでのたうち回るがいい!」
「ち、ちくしょう!」
「フン、大した時間稼ぎにもならなかったな、佐伯。とどめだ。最後は背中から胸にかけて貫いてやろう!」
威追が両手に剣をかまえ、頭上にかざした。その時、
ポーン!
と軽い音をたて、赤い小さな物が闇の中から跳ねてきた。威追達は眉をしかめた。丸い物体は、連中の周囲を遊ぶように飛び跳ねた。よく見るとそれは手鞠だった。
「何だ、これは?」
続いて、別の方向の闇の中から、今度は青色の手鞠が飛び出してきた。それも同じく威追達の周囲を跳ね回っている。
「?」
最後に、今度は真っ白な手鞠が別の闇から飛び出し、それも他の鞠に混じった。鞠の中からは、楽しげな童女の笑い声が聞こえてきた。クスクスッと野原の花達をくすぐるような、優しい春の風のようだ。
「これは何だ!」
威追がそう叫んだ時、不意に三つの手鞠の動きが止った。それは連中の周りで、三角形の形を成していた。
「何?」
突然、赤、青、白、それぞれ三つの色の手鞠から、一気に頭上に向けて光が飛び出した。それらの光は頭上で一緒になり、輝き始めた。
「しまった!」
威追が叫んだがもう遅い、三つの手鞠が形成した結界は、そう簡単に壊せる代物ではなかった。再び、悪戯っぽい童女の笑い声が聞こえてきた。
「誰だ?ああ!ことだまじゃないか!」
「大丈夫でちゅか?」
ことだまはニコッと笑うと、その黒い艶のある髪を耳元で、跳ねるように揺らした。
「どうしてここに?」
「説明は後でちゅ。早く逃げるでちゅ」
ことだまは僕の手を取ると、トコトコと走り出した。闇の中をそのままどんどん突き進んで行く。びっこを引きながらも、僕も後に続いた。
「おい、どっちに向かってるんだ?」
「出口でちゅ」
「どうしてそんな事が分るんだ?」
「自然に分かるでちゅ」
「お前は、やっぱり普通の子供ではなかったんだな」
「光司は昔から知っているでちゅ。いつも見ていたでちゅ」
「見ていた?どこから見ていたんだい?」
「空の上でちゅ」
「まさか宇宙じゃないよな」
「違いまちゅよ」
ことだまは、ころころと笑った。
「天女ちゃまと見ていたでちゅ」
そう言った時、ことだまは不意にこっちを向いてしゃがみこんだ。
「何だ?」
「座るでちゅ。傷の手当てがいるでちゅ」
「ああ…うん」
闇の地面に座り込むと、ことだまは僕の傷の上に手をあてた。治療のつもりなのか?
「!」
驚くべき事に、ことだまの手からは様々な色の細い光が飛び出し、それが傷口の周囲を回った。するとあれ程、ひどかった傷口が静かに閉じられていくのが見えた。
「不思議だ、ちっとも痛くないぞ」
「良かったでちゅ」
「お前は色んな事で役に立つんだな。見直したよ」
ことだまはエヘヘと笑った。
「あたちは、光司のそばに行くように、天女様に言われたでちゅ。だからずっと一緒にいるでちゅ」
「その天女様って、誰だい?」
「その説明はここを出てからするでちゅ」
ますます不思議な子だった。小さな子供の割には、妙に僕を諭すような喋り方をする時がある。いずれにしても、頼もしい限りだ。手当のおかげで早く走る事ができた。
辺りは相変わらず、何も見えない真の闇だというのに、ことだまは漆黒の髪をしゃんしゃんと揺らしながら走って行く。今は黙ってついて行くしかない。
不意に闇の彼方に一筋の明りが見えてきた。
「あれが出口でちゅ。急ぐでちゅ」
ことだまのいう通り、必死で急いだ。だが、幾ら走っても走っても、その明りはなかなか大きくはならなかった。ますます遠退いて行くような感じだ。
「ことだま、どうしてなんだ?幾ら走っても変わらないぞ」
「…」
ことだまは突然、立ち止まると暫しの沈黙の後、呟いた。
「失敗したでちゅ」
「失敗?」
ことだまが額に汗を浮かべ、後ろを振り返った。すると不意に闇の中の一部分が動いたかのように見えた。何かがいるのだ。
「クククク…」
闇の中から再び威追たちの笑い声が洩れる。何て事だ、あの出口の光は奴らの幻術だったのか!
『まさか赤ん坊の技に翻弄されるとはな。面白い、楽しませて貰ったぞ。だが、あんな初歩的な結界、理屈さえ分れば壊すのはたやすい事だ』
暗闇の中に威追のうすら笑いが浮かぶ。
「ちくしょう!」
『佐伯、赤ん坊に助けて貰わないと逃げられないのか、よくもその程度で鬼芭王と戦えたな。ククク』
「ことだま、お前だけでも逃げろ!」
「駄目でちゅ」
突然、ことだまは力が抜けたかのように足下に倒れ込んだ。
「どうしたんだ!」
「さっきの結界で、いっぺんに力を使い過ぎたでちゅ。ごめんなさいでちゅ」
ことだまは、大粒の汗を額から流し、ハアハアと息を荒くしていた。苦しいのか?
「ことだま、しっかりしろ、しっかりするんだ!」
『小僧、人の心配よりも、自分の心配をしたらどうだ?』
「何!」
『冥土の土産に俺の召喚術を見るがいい!』
威追はそう言うと、片手を闇の中にスッと伸ばした。
『威追の名において命ずる。い出よ、迷企羅神(めきらしん)!』
闇の中におびただしい水蒸気が発生し、その熱で全身が焼けるような熱さを感じた。何かが生まれようとしている。やがて何もないはずの空間から、不気味な存在が息づくのを感じた。その音を聞いただけで震えが走った。
「グオオ!」と呻き声が洩れた。
『我が下僕、迷企羅よ、目の前にいる小僧を始末しろ!』
背後でシャン!という金属的な音が響いた。
「な、何の音だ?」
次の瞬間、ことだまが絶叫した!
「光司ー、逃げるでちゅ!」
ズドッ!
鈍い音が左手で響き、稲妻のような閃光が一瞬走った。
次の瞬間、ボトッと音を立てて何かが足下に転がるのが見えた。
「何だ?」
足下に目をやると、人間の指先のようなものが見える。視線をずらして行くと、手首や腕の部分まで見えた。体の左側がすっと軽く感じられた。
「あ…」
足下に転がっている物と、自分の思考が結びつくまでに時間がかかった。
「ま、まさか…」
転がっていたのは自分の左腕だった。瞬間、右手を傷口に持って行った。
「う、嘘だろ?」
「佐伯、お前の左腕、この俺が貰う!」
不意に威追が突進して来た。茫然としているところを足技でなぎ払われた。
「うわああ!」
「ククク、今頃泣き叫んでもおそいぞ。ついでにこの赤ん坊も貰って行くぞ!」
瞬間、カッとなった。
「やめろー!」
「その体で俺に立ち向かうか」
強烈な足蹴りが容赦なく、腹部に叩き込まれ僕は後ろに転がった。
「ぐぇっ!」
このまま死ぬのか?こんな異世界の闇の中で…嫌だ。
意識の奥で最後の抵抗を試みる。だが、それさえも儚く消えつつあった。
闇が全てをおおっていく。意識の中にしたたる闇、幾重にも幾重にも、厚いカーテンのように新しい闇が生まれては目の前を覆っていく。
「!」
闇の中に、ちらりと何かが見えた。小さな花だ。桜だ。桜の花びらだ。それからゆっくりと…ゆっくりと体が持ち上がるのが感じられた。
|
|