おぼろげな意識の中、桜の花びらが舞うのを見ていた。たくさんの花びらが風に吹かれて舞い踊る光景は、この世のものとは思えない。それらが自分の周囲を取り囲んだ時、少しずつ体中の傷が癒されていくのを感じた。肩から切断された左腕を除いては。
やがて、その不可思議な力が体内の中枢神経に作用し、眠りの底から意識が覚醒しようとゆっくりと頭をもたげた。
柔らかな光の中で静かに目を開いた。どうやら死んではいないらしい。
頬にあたる涼しい風がその感をいっそう強めた。
「ここは…どこだ?」
あの夢と同じだ。辺り一面、桜の世界。幾重にも重なった桜の木がどこまでも続いている。もしかするとまた同じ夢を見ているのかとも思ったが、あの時とは違い、肩の傷の痛みははっきり残っていた。
やがて、おだやかな風が吹くと同時に、目の前の桜の壁の一部がわずかに開いた。不自然に左右に押し広げられた桜の中に一つのトンネルができているのが見えた。
良かった、何とか起きられるようだ。さっき感じた通り、あばら骨やその他の部分も綺麗に直っていた。一体、なぜなのか…。
長いトンネルを抜けた後、いきなり視界が開け、だだっ広い野原のような場所に出た。そして目の前には僕を待っていたかのように一人の少女が立っていた。誰だ?
「あなたが佐伯光司?」
鈴の音のように、涼しげに響く声…。腰の辺りまである茶色の長い髪が印象的だった。
この子は、あの天女の仲間なのか?
少女は小袖の上に桜色の上衣を着ており、それも歩く度に風にゆらりと揺れる。膝元までしかない着物の下からは真っ白な両足が見え、それが雪の色を連想させて眩しかった。透き通るような白い肌に、瞳の赤はどこまでも澄んでいて、そのまま吸い込まれそうな気がした。
「あなたは、誰ですか?」
「私の名は鈴魅亜(れみあ)、ついて来て」
鈴魅亜と名乗った少女は、こちらに背を向けると、そのまま歩き出した。
「あの…」
「何?」
「ここは、天国なのかい?」
少女は片方の眉を上げ、微かに笑ったようだった。
「天国とは場所ではないわ、完全なる状態をさす言葉…」
少女はそのまま黙って歩いて行く。一面桜の木が植えられている丘をいくつも越えた。少女の歩くスピードは早く、ついて行くのがやっとだ。
周囲の桜は、奥に行くにしたがってますます華いでゆく。あまりの桜の数に息が苦しくなる
「今は秋なのに、なぜ桜が咲いているんだい?」
「ここには、そんな季節感は必要ないの」
「一体ここはどこなんだ? もしかして極浄浄土とか?」
「ここは吉野山…」
「確かに吉野は桜が多いけど、今は咲いてない筈だよ」
「あなた達のいう吉野山とは、少し違うの」
「どういう事?」
「ここは、あなたたちが通常見ている吉野山の裏にあたるの」
「裏?」
「そう。もう一つの吉野山といってもいいかな。でも、もののとらえ方や解釈の仕方は人それぞれ。嘘だと思うなら上を見てごらん」
僕は空を見上げて、思わず絶叫した。
「ば、馬鹿な、空に吉野山が!」
驚くべき事に、頭上にはもう一つの吉野山が存在していた。こっちから見ると完全に逆さまである。たくさんの葉緑樹が山を覆っていて、野鳥が飛び交う姿まで見えた。しかし、その吉野山には桜は咲いていない。あっちが表という事だろうか?
「あれが、あなた達の吉野山よ」
「あそこから、こっちは見えないのか?」
「普通の人間にはまず見えない」
ここは吉野山であって吉野山ではない。一体、どう解釈したらいいのだろうか?
やがて、目の前に寺が見えてきた。周囲の桜に今にも飲み込まれそうなほど小さな寺だったが、それでも荘厳な雰囲気を漂わせていた。
境内の中を黙って進んだ。本殿の扉を開けると、中には法隆寺の夢殿を思わせるような、八角形の小さな円堂が建っていた。
少女がその前で言った。
「佐伯光司を連れて来たよ」
「ありがとう」
優しく落ち着いた声と共に、八角堂の扉が開かれた。途端に中からたくさんの桜の花びらが、舞い出し、それが本殿全体に広がった。
舞い散る桜の花びらの中にその人は立っていた。あの天女だった。桜の中に流れる黒い髪。途端に春の香りがあたりを包んだ。
「君は、夢に出てきた人?」
目の前の天女はわずかに頷いた。
「待っていました。長い間」
「僕の事を知っているのですか?」
「ええ、ずっと昔から…」
「あなたは誰なんです?」
天女は答えなかった。
「さあ中にお入り下さい」
促されて円堂の中に入った。
「うわあ」
その部屋の中には広大な宇宙が開けていた。無限に続く大宇宙、その中に無数の星々が瞬いていた。巨大な銀河や様々な色の星雲が、手に取るように眼前にあった。その存在感はそれがすべて本物であることを示していた。 慌てて外へ飛び出して円堂を見ると、とても小さな建物だった。小屋のような感じだ。それが中に入ると突然、こんなすごい光景が広がっているなんて…。
「ここは私がいつも暝想をしている部屋です」
「これが部屋?」
「ええ。さあ、入って」
いきなり鈴魅亜に背中を押された。しかし部屋の中の宇宙には床も何もないのだ。
「わあ、待って、落ちる落ちる!」
夢中で手足をバタバタさせると、二人がクスッと笑った。
「大丈夫です。ここは宇宙の姿を、幻影として映し出しているだけですから」
「ああ、びっくりした」
胸を撫でおろしていると、天女がフワリと目の前に座った。大宇宙を背にした天女の姿は、とても神秘的だ。
天女は暫く僕を、何かを確かめるかのように見つめていたが、やがて静かな口調で話し始めた。
「佐伯さんは善界の血をひかれる方ですね」
「ええ」
天女は何もかもお見通しのようだった。
「傷の具合はどうですか?」
「何とか、ただ左腕が…」
迷企羅に斬り落とされた左腕、あれを何とか取り戻さないと…。
天女は少し悲しそうに目を伏せた。瞳の色が少し変わった。
「ごめんなさい。もう少し早く助けてさしあげる事ができたら良かったのですが…亜空間の場所が特定できなかったのです」
「あの時はもう駄目かと思いました。ことだまが来てくれなかったら」
そう言った途端、不意にことだまの笑顔が頭の中に浮かび上がった。
「そうだ、ことだまは? あの子はどうしたんです。こんなところでのんびりとしている場合じゃない!」
立ち上がろうとしたところを、鈴魅亜が慌てて制した。
「待って、ここで慌てても同じ事。その体じゃ何もできない」
僕は彼女の手を振り払いながら怒鳴った。
「あの子は僕の代りにさらわれたんだぞ、今頃、拷問されているかも知れないっていうのに!」
不意に鈴魅亜の赤い目がカッ! と見開かれた。その途端、体の力が抜け、僕はペタンとその場に座り込んだ。
「ことだまは大丈夫、心配いらないわ」
「どうして分るんだ?」
「あの子の発している気で分るの。今のところはまだ大丈夫よ。それに阿修羅の目的はことだまではなくて、あなたよ」
「それだったら、なおさら早く行かなきゃ」
「そんな体で? 五体満足でもかなわなかったたじゃない!」
「うっ…」
図星を刺され、目を伏せた。確かに鈴魅亜のいうとおりだ。このまま行ってもまた返り討ちに決まっている。しかし、それでも行きたかった。
「本当にどうしたらいいか、考えるのよ」
僕の震える右手の上に、鈴魅亜の手が静かに重ねられた。澄んだ赤い瞳が心を落ち着かせた。「分った。いうとおりにするよ。でもどうしたらいい? 左腕がないと、善界の弓も召喚できないんだ。今の僕には何も…」
急に情けない気持ちに襲われ、目頭が熱くなって目の前がぼやけてきた。
「泣かないで。佐伯さん」
天女が言う。
「佐伯さん、私の話を聞いて下さい。これはあなたの今後を大きく左右する事なのです」
天女に優しく諭されて、急に自分が子供になったような気がした。
「分りました。聞かせて下さい」
「遥か昔から、私はこの場所で監視し続けてきました」
「何の監視を?」
「クワィロゥ…」
天女の口から、不思議な言葉が洩れた。
「魔界と人間界との接点です」
「そんなものがあるのですか?」
天女は頷いた。
「いにしえより妖怪や鬼、魔神達は、このクワィロゥを通って人間界へ侵入しています。それを監視してきたのです」
「それはどこにあるんですか?」
「クワィロゥは一つだけではありません。様々な場所に、色々な形で存在しています。
私が監視できるのはヤマトの国の中だけです。このヤマトだけでも至るところにクワィロゥがあります」
そんなものの存在は後藤氏からも聞いた事がなかった。
「おそらくあなた達のお仲間には、その存在を知る人はいないでしょう。ただ一人の人を除いて」
「誰です?」
「亡くなった谷山晃一さんです。あの方はよくご存知でした」
「谷山教授を知っていたのですか!」
「ええ。何度かお話しをした事もあります」
「驚きだ。谷山教授と知り合いだったなんて!」
「谷山さんに、信頼のおける親友がいる事は存じていました。あなたはその方と行動を共にされてるのですね」
「はい。一緒に京都で谷山教授の仇を討ちました」
「鬼芭王が倒された時、その轟きはこの吉野まで伝わってきました」
「凄い大爆発でしたから。ところで、そのクワィロゥですが」
「はい?」
「どうにかして破壊する事はできませんか?」
天女は一瞬、あっけに取られたような表情になった。
「どうしてですか?」
「奴らはクワィロゥを通って侵入して来てるんでしょ? それだったら通路を破壊してやれば、人間界には来れなくなるんじゃないかな」
「それは…確かにいい考えです。でも、クワィロゥはその存在事態が極めて不安定で、常に移動しているのです」
「まさか、自分で動いているんですか?」
「暫くある場所にとどまっているかと思えば、急に姿を消したりします。そして今度はまるで別の場所に出現する事もあるのです」
「そうか…予測も特定もできないのか。まるで生き物みたいだ」
「それに、クワィロゥはいたる場所に無数に存在します。全部を破壊する事は困難でしょう。それに、そのひとつを破壊するにもかなりの法力が必要です。でも、谷山さんはそれも考えておられたのです。だから悪魔に命を狙われたのでしょう」
「そうだったのか…」
「あなた達が京都で滅ぼした鬼芭王も、勿論、その昔クワィロゥを通って来ました。そういった悪魔が現れた時、私は何度も人間たちに向けて信号を送ってきました。もちろん、力がある人にだけですが」
「春日ホテルで僕に見せた夢ですね?」
「はい」
「そして谷山教授も、その夢を見ていた」
「ええ、あの方は人間の中では特にそういったものに理解を示される方でした。だから夢の中でも私の声が聞こえたのだと思います。普通の人には私の姿は見えませんし、声も聞こえません」
「一つ、分らない事があるんです」
「何でしょうか?」
「阿修羅の事です。どうして興福寺の阿修羅像が、勝手に動き出したんでしょう?」
「それを説明するには、少し時間をさかのぼらないといけません」
天女はすっと立ち上がると、隣へ来て静かに腰を降ろし、白い手を宇宙に向けた。
「あれを見て下さい」
天女が指差す方向に、二体の神像が、さらに別の場所には阿修羅の像が現れた。
「これは?」
「遥か昔、この星では世界を焼き尽くす程の、凄じいいくさが起こりました。その時一度、地上のあらゆる者は死に絶え、全ては灰と化したのです。この事は今では伝説として残されているだけで、それすら知る者も少なくなりました」
「何と何が戦ったのですか?」
「この阿修羅と、上に幻影として映っている神、インドラとブラフマンです」
「確か古代インドの…」
「そうです。もともと阿修羅はインドラ(帝釈天)という戦いの神と戦っていたのです。阿修羅は地獄の劫火で世界を焼き尽くそうとし、インドラは雷撃や様々な超能力でそれを阻止しようとしていました」
「ひええ、さぞかし恐ろしい戦いだったろうなあ」
「そしてある時、ついに雌雄を決する時が来たのです。阿修羅の余りの非道さに怒ったインドラは、ブラフマンに助けを請い、共に戦ったのです。さすがの阿修羅も、二柱の神の前ではその霊力が及びませんでした。さんざん世界を焼き尽くした後、最後に胴体を二つに折られて、今でいうインドの南部に沈み、地中深く埋もれてしまったのです」
「そんな事があったのですか」
「そして、言い伝えでは阿修羅を再び目覚めさせないために、その阿修羅が沈んだ場所に寺院を作り、これを封印したとのことです。そして選ばれたバラモンの僧たちが、その寺を守ってきたのです」
聞いただけでも恐ろしい話だったが、あまりにスケールが大きすぎてピンと来なかった。
この事を話した時から、なぜか天女はその白い顔をうつむかせた。この事に何か特別な想いがあるのだろうか? 唇が微かに震えているのが分った。
「どうしたのですか?」
「いえ、何でもありません。それから…」
天女は言葉を続けた。
「それから何百年かたって、一人の悪魔がクワィロゥを通り、その寺院に訪れたのです」
「悪魔? まさか…」
「そう、それがあの威追(いお)だったのです。威追は邪教の神の使い魔でした。彼はそこにいた寺院の僧たちを皆殺しにし、封印されていた阿修羅の神霊を奪っていきました」
「あの、神霊って何ですか?」
「平たく言えば魂の事です。阿修羅は肉体は滅びても、その神霊はちゃんと生きていたのです」
「何て事だ。でも阿修羅の体は既にボロボロだったんでしょ?」
「威追はまず弱っていた阿修羅の神霊を、時間をかけて元通りにし、そしてそれを興福寺の中にあった阿修羅像に埋め込んだのです」
「そんな事ができるのですか!」
「威追は長い間、日本のいたるところで悪事をくりかえしてきました。京都に鬼芭王を送り込んだのも威追です。そして、彼はそれらの活動によって集った負のエネルギーを弱っていた阿修羅の神霊に与えたのです。そのありようが違うとはいえ、悪魔の負のエネルギーは全て同じです。こうして阿修羅の神霊は日増しにその力を取り戻していったのです」
「じゃ、僕と田村さんがあの時、興福寺で出会った阿修羅がそれだったのか」
「佐伯さんは、ちょうど邪神の復活に居合せたのです」
「では、とにかくあの阿修羅を叩く必要があるのですね?」
「そうです。さもないと再び世界が地獄の劫火に包まれ、あらゆるものが灰と化してしまうでしょう」
興福寺で阿修羅が放った劫火を思い出した。あれが世界を焼き尽くすのか?
「大丈夫ですよ。僕等にはまりちゃんがいるから」
「あなた達の仲間のお人形ですね?」
「既にまりちゃんは一度、阿修羅と一戦交えています。まりちゃんだったら阿修羅を倒せるはずだ。あの鬼芭王でさえ琵琶湖に葬ってしまったくらいですから」
「それでも油断はなりません。なぜなら、あの興福寺の段階の阿修羅はまだ完全体ではなかったからです」
「か、完全体じゃない? あれで!」
「阿修羅もはじめは新しい神体に馴れていませんから。しかし、時間がたつにしたがってあらゆる能力が、先のいくさの時に近づいていく事でしょう」
「それは大変だ!」
ゴクッと唾を飲んだ。全く、阿修羅といい威追といい…ロクな事がない。善界の末裔である僕の一生は呪われているんじゃないだろうな。
「あなた達ははじめ、京都にあるクワィロゥを破壊しました」
「鬼芭王と戦った大沢の池の事ですね?」
「そうです。そして、クワィロゥは次に興福寺に現れました」
「阿修羅がいたところだ。そうか、それで胡蝶は搭の中に何かがあると言っていたのか」
「そして、次が東大寺の大仏殿です」
「ブラックマリー達と戦ったところだ。確かにあの建物も崩れてしまった」
「今度はどこに現れるのかしらね」
鈴魅亜がそう言った時、不意に威追が最後に言った言葉を思い出した。
「そうか、斑鳩だ。奴は斑鳩に来いと言ったんだ!」
「どうりで斑鳩寺の場所で、クワィロゥの反応が始ってるわ」
「斑鳩寺ってどこにあるんだ?」
「法隆寺の事よ」
「奴らは法隆寺から魔界に帰るつもりなのか」
「斑鳩に行けば奴らの思うツボよ。罠を張って待っているわ。さっきも言った通り、このままあなたを行かせる訳にはいかない!」
「そんな、だったらどうしたらいいんだ?」
鈴魅亜は一瞬考え込んでいたが、やがて僕の方に向きを変えると、おもむろに言った。
「仕方のない人、じゃあ、ついて来て」
すっと立ち上がる鈴魅亜の後に続く。どうやら何かが見えてきそうな気がした。
「私も参ります。佐伯さんが心配ですから」
天女はそう言うと立ち上がった。何だか保護者同伴のような気恥ずかしさを感じる。
不思議な事に、天女が円堂を出た途端、中にあった宇宙空間は消えてしまい、ただの木でできた殺風景な部屋が見えているだけだった。境内から外に出て、並んで桜並木を歩く。
「どうしてことだまを僕のところによこしたんです?」
「これからのあなたに必要と思ったからです。あの子はどんな異郷に行っても暮す事ができます。それにどんな国の言葉でも喋れますよ。あなたが負った傷も直す事ができます。これからは色々とあなたの役に立つ事でしょう」
「あの子の正体は何なんですか?」
「ことだまは、読んで字のごとく、言に霊と書きます。ことばの妖精です」
「妖精!じゃ、鈴魅亜も!」
「鈴魅亜は鈴の妖精…でも、この子は元は人間の子でした。ある理由で私が妖精にしたのです。それは、じきに本人がお話するでしょう」
「こっちよ」
鈴魅亜が指で示した方向は、急な坂道になっていた。足下に気をつけながら降りる。
天女はそのまま音もなく宙に舞い上がり、羽衣を風になびかせながらついてきた。
しかし、吉野天女は一体、どこから来たのだろうか? 頭上を自在に飛び回る天女を見上げて思った。
彼女は始めからここにいたのだろうか? 威追たちは“小娘が生きていた”と言った。あれはどういう事なのだろうか? 何かそれには触れてはならないような気がした。
天女が頭上で微笑んだ。心を読まれているみたいだ。慌てて視線をそらし、その疑問を唾と一緒に飲み込んだ。
さらに下って行くと、目の前には、少し離れた場所に際だって大きな桜があった。鈴魅亜がその木に近づいた。
「この桜の木の下で、その昔ある方が修業をしたの」
「ある方って誰だ?」
「ふふ、今は教えられないわ」
鈴魅亜はそう言うと、そこら辺に落ちていた棒で地面の上に線を引き始めた。
「何だい、それ?」
「結界よ」
茶色の髪の少女は、チラリとこちらを見て呟いた。
「結界?」
「今からここに、結界を張るの。周囲に影響を与えないようにね」
線を引き終えると、鈴魅亜は棒についた泥を払い、どこから用意したのだろうか? 一振りの刀をすらりと抜き、それを僕の目の前に差し出した。陽光の中で刀身がギラリと鈍い光を放つ。
「な、何?」
「持つのよ」
思ったよりズシリと重い。日本刀ってこんなに重いのか?
「これで、何をするんだ?」
「ふふ、それで桜を斬ってみて」
「ええっ、桜を?」
「木を斬るんじゃないの、舞い落ちてくる花びらを斬るの」
目の前にはおだやかな風と共に、無数の花びらが落ちてくる。これを斬れというのか?
「でやっ!」
気合いを込めて刀を左右に振った。だが、桜の花びらはそれをからかうかのように、辺りに舞い散ってしまった。鈴魅亜がクスクスと笑った。
「どうしたの? それじゃ何にも斬れないよ」
「でも、花びらが逃げちゃうよ!」
「借しなさい」
鈴魅亜は刀を受け取ると、それを右手に持ち、ゆっくりとかまえた。おもむろに刀を頭上に上げたかと思うと、ピタリと弧を張った。どの位置からも斬り出せる姿勢だ。
一瞬の沈黙の後、鈴魅亜は静かに目を閉じる。やがて頬をなでるような風が吹いた時、彼女の頭上の刀がすっと流れたかのように見えた。それが舞い落ちてくる花びらの間に静かに入り込む。
「あっ!」
驚いた事に、一つではなく、幾つもの花びらが真っ二つになり、他の花びらとは別の方向に流れて行った。
「今のが要領よ」
「でも、僕がやると、花びらは逃げちゃうよ」
「ならばどうすれば斬れるか、自分で考えなさい」
鈴魅亜は僕に背を向けると、そのまま立ち去ろうとしていた。
「ええっ? もうどこかに行っちゃうの?」
「あなたは、その桜が斬れるまで、そこにいるのよ。もしも花びらを斬る事ができたら、天女様がある術を授けてくれるわ。だけど、その術を使うのには、風を理解していないと駄目なの」
「そんな、そんな暇はないよ!」
「佐伯光司、どこまで甘えれば気がすむの!」
鈴魅亜は顔を歪め、鋭い一喝を発した。
「確かにあなたは今まで、善界の弓を自在に操ってきたわ。だけど、それはあなたが、善界の血を引いていたというだけ。長年の修業の末に身につけた力ではないわ」
「それは、そうだけど」
「あなたに術を授ける前に、最低の事は分ってもらわないといけないの。あたしだって、何年も血の滲むような修業をして現在の力を得たのよ。あなたは例えその一部とはいえ、それをたったの数時間で得ようというの?」
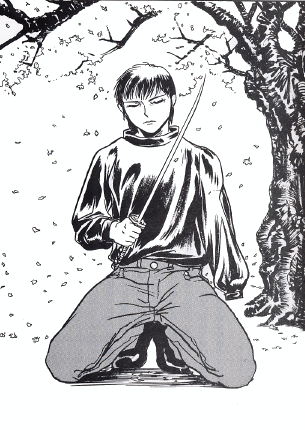 「うっ…」
「うっ…」
「本来ならばこのやり方も、あたしに言わせれば無茶な教え方。だけど、そこは善界の子孫であるあなたの才能にかけてるの。いい? 決して焦って自分を見失ってはいけない。もっとどっしりと腰をすえて色々と考えなさい」
「桜が斬れなかったら、どうしたらいいんだ?」
「その時はじっと座って暝想するのよ。言っとくけど、これは剣術の修業ではないわ、あくまで風を理解するのよ」
ここまで言われたらやるしかない!
「分った。やってみる!」
とうとうその日から、修業をする事になってしまった。ことだまの事も心配だったが、鈴魅亜のいう通り、このまま威追に立ち向かってもまた返り討ちにあうだけだ。
僕は桜の木の下に座り込み、暝想する事にした。こんな経験は初めてだ。辺りに舞う花びらを見ながら、じっと目をつぶった。
…同じ頃、火川神社にて…
「一体、佐伯さんと、ことだまちゃんはどこに行ったんでしょうね?」
袴姿の林田が、先程から両腕をじっと組んだまま首をかしげていた。
後藤氏もじっと目をつぶり、指先でテーブルをトントンと叩きながら、何事か考え込んでいる様子だった。食事が終わった後、超常現象調査会のメンバーはずっと考え込んだままなのだった。まりちゃんと胡蝶も座布団の上で天井を見つめ、ひそひそと何かを相談しているようだった。
「うっかり目を離したのがまずかったかな」
林田は独り言のようにつぶやく。
「まあ、仕方ないでしょう。不可抗力ですからね。それにね、私はなぜか彼が無事のような気がします」
後藤氏は相変わらず、じっと目をつぶって指先をトントンと、テーブルの上で弾いていた。おそらく後藤氏が集中する時の癖なのだろう。あの白髪混じりの頭の中では今、様々な思考がフル回転しているに違いない。
重苦しい雰囲気の中、奥の部屋で占っていた玲子が戻ってきた。
林田が慌てて聞いた。
「どうだった?」
「駄目、色んなところに気を飛ばしてみたけど、やっぱり反応がないわ」
「という事は、やはり胡蝶のいう通り、通常の空間ではないのかな」
「玲子さん、御苦労様でした」
後藤氏が暝想を中断し、ねぎらいの言葉をかけた。
「申し訳ありません、お役に立てなくて。明日、もう一度行やってみます」
「ん?」
玲子は怪訝そうに首をかしげた。
「どうした、玲子?」
「お兄様、何か聞こえませんでした?」
「何が?」
「いま鈴のような音が」
「鈴の音?」
『まりこにも聞こえたわ!』
「本当かい? でも、妙な奴がいたら狛犬達が発動するはずだけどなあ」
林田がそう言った時、また庭の方でチリリン、と鈴の鳴る音がした。
「何の音ですかね?」
後藤氏が窓を見ながら言った。
玲子は立ち上がって窓の外を見た。しかし、外には石灯篭や庭の松の木しか見えなかった。
「変ね。誰もいないわ」
「玲子、鳥居の上を見ろよ」
林田がそう言った時、階段を登りきったところにある朱塗りの鳥居の上に、誰かが立っているのが分った。月光の中にシルエットが浮かび上がった。
「誰?」
「表に出てみよう!」
全員で座敷から庭の方に出ると、確かに鳥居の上の人影はそれに反応した。そいつは鳥居の上に座り込み、後藤氏たちが近寄るのを待っていた。
「あなたは誰?」
玲子の声が夜の境内に響き渡る。それに反応するかのように、再び鈴の音がチリリン、と鳴った。
次の瞬間、そいつはそのまま膝を曲げて大きくジャンプをすると、月光の中で何度も回転しながら地面に降り立った。人間離れした着地を見せたのは一人の少女だった。
「かっこいい!」
林田が思わず拍手をする。
少女は顔色も変えず、茶色の髪を揺らしながら近づいてきた。彼女は小袖を着た、赤い瞳の娘だった。一同は目を丸くした。
「あの、どちらさんですか?」
「こんばんわ、超常現象調査会の皆さん。私は鈴魅亜(れみあ)、吉野山から来たの」
「吉野山ですか?」
「そうよ。今日は佐伯さんが無事な事を知らせに来たの」
「何だって!」
一同は一斉に鈴魅亜を取り囲み、そのまま社務所の中に招き入れた。
「佐伯さんは今、どうされているのですか?」
鈴魅亜を座布団の上に座らせ、玲子が入れたお茶を差し出しながら、後藤氏は言った。
「佐伯さんは威追たちが作った亜空間の中で、酷い傷を負ったの。それから天女様に助けられて、今は吉野山にいるわ」
「変だな。吉野山なら玲子さんも気を流して占ったはずなんだけど」
「あたしたちがいる空間は、普通の吉野山ではないの。吉野山に鏡のようになって対峙している、もう一つの吉野山なの」
「なるほど、パラレルワールドという訳ですか。これは面白い」
後藤氏とまりちゃんがニコッとした。
「佐伯さんは威追が召喚した迷企羅神と戦って、左腕を失ったの。その腕とことだまを取り戻すために、斑鳩寺に行く事になっている」
「なるほど、法隆寺の事ですね」
「斑鳩寺には今、威追たちが魔界と人間界を往来しているクワィロゥという、特殊な通路ができているの。そこに佐伯さんをおびき寄せるつもりよ」
「何と、そんなものがあるのですか!」
驚く後藤氏たちに、鈴魅亜はクワィロゥの事、天女とことだまの事、そして最後に太古の昔に起こった阿修羅大戦の事を詳しく話した。
それを頷くように聞いていた後藤氏は、丸い目をいっそう丸くして言った。
「やれやれ、今回の事件にはそんな、とてつもない因縁があったのですか。しかも、そういう世界があるとは驚きですなぁ。できたら一度、覗いてみたいものです」
「普通の人には無理よ」
「まあとにかく、佐伯さんが無事で良かったですよ」
誰もがほっとしたように頷いた。胸につかえていたものが取れたような感じだった。
「後藤さん、そうすると例の停電の事も、説明がつきませんか?」
「そうですね。クワィロゥが出現した地域は、何等かの妨害現象に見舞われるという事でしょう。となると、逆を言えばそういった現象が起きた地域はクワィロゥの存在の目安となりますねぇ。これは大いに研究するに相応しいテーマです」
後藤氏の知的好奇心がムクムクと頭をもたげてきたのが分かる。
玲子が座敷の角で、そっと胡蝶を抱いて言った。
『胡蝶、光司は無事だって。良かったね』
『ウン!』
胡蝶の顔にほっと安堵の表情が出た。張り詰めていた緊張から解かれたのだろうか。
だがその時、不気味な影が火川神社に近づいているのを、気づいた者はいなかった。
神社の入口を守っている狛犬たちでさえ、敵の奇襲になす術もなくやられていた。佐伯が無事だったという安心感からか、さすがの林田兄妹もこの時ばかりは油断していたのだ。音もなく忍び寄る影…。
不意に障子に不気味な影が映ったのを見た時、誰もが驚愕した。ある者は銃を取り、ある者は武闘のかまえをした。その刹那、社務所の障子やガラス窓は粉々に打ち砕かれ、冷たい秋の冷気が部屋の中をかけ巡った。月光をバックに佇む男がいた。
『ふふ、そんなに小僧が心配だったか』
「お前は威追、生きていたのか!」
『舐めるな。そのヒトガタのエネルギーくらい、よけるのは造作もない事だ』
「獅子たちはどうしたんだ!」
『くく、あの番犬の事か? ただの狛犬に戻ってしまえば俺の敵ではない。獅子へと変化する前に片付けてやったぞ。もっともノラ犬を倒したとて大した自慢にはならんがな』
まりちゃんと胡蝶が打撃を加えようと、飛び上がった。だが、二人の攻撃を紙一重でかわすと、回し蹴りが唸りを上げてまりちゃんに襲いかかった。
「!」
何とかガードをして蹴りを防いだが、恐ろしい力で外に弾き飛ばされた。まりちゃんが、外に群生していた杉の木にぶつかると、周囲が何メートルもある大木が、音をたてて折れた。
『鬼雷獣!』
呪文を唱えて、召喚術を使おうとする胡蝶の両手に、威追の手が覆い被さる。途端に発生させようとした鬼雷獣は捻り潰され、その反動が胡蝶に襲いかかった。
『グッ!』
『術を潰されて苦しいか、ヒトガタ!』
威追の拳が突き出されると思ったが、次の瞬間、悪魔は胡蝶を手に抱えたまま、屋根を突き破り、宙に飛び出した。必死で威追から逃れようとする胡蝶を、悪魔の怪力が締め上げる。
『ククク、暫くお前で遊ばせてもらおう』
威追は人差し指と中指だけを突き出し、それを胡蝶の額にあてた。途端に悪魔の口から呪文が流れ、それが胡蝶の額に吸収されていく。なす術もなく、胡蝶はそのままガックリと首を垂れた。
『ククク、これでよかろう。後は佐伯光司だけだ』
威追は胡蝶を宙に放り投げる。それをまりちゃんが、両手でキャッチした。
「待ちなさい、威追!」
その時、屋根の上から細く、鋭い一喝が飛んだ。ゆっくりと振り返る悪魔。
『ほう、誰かと思えば、ヴァスティに助けられた死にぞこないの小娘か。まだ生きていたんだな』
「威追、お前に復讐するまであたしは死なない!」
『小娘の相手をしている暇はないわ! 佐伯光司に伝えろ、斑鳩寺で待っているとな!』
そう言い残すと、悪魔は低く笑いながら闇の中へと消えた。そして後には不気味な程の静寂が蘇り、辺りには冷たい秋風が吹いていた。
…それから一週間後、再び吉野山…
あれからどれくらい、時間がたったのか。相変わらず桜の花びらは斬れないままだった。
何度、刀を振り回しても、何度座禅を組んでみても、結果は同じ事だった。
もういい加減に嫌になってくる。それでもやめる訳にはいかなかった。ここでやめたら、全てが振り出しに戻ってしまう。焦る僕の気持ちとは裏腹に、桜は相変わらず華やかだ。
他の超常現象調査会のメンバーも、自分を心配している事だろう。胡蝶の奴はどうしただろうか? きっとすごく心配しているに違いない。連絡を取りたくても、こんな異世界からでは思念波を送る事は無理だ。どちらにしろ、早く新しい術を覚えるしかないのだ。
「ご休憩ですか?」
突然、透き通る声が頭上から聞こえてきた。慌てて身を起こすと、天女がすぐそばの空間に浮かんでいた。
「あっ、あははは、どーも。ちょっと疲れたもので」
「クスッ、さっきからずっとその調子でしたよ」
いきなりバレていた。
「だいぶお困りのようですね」
「ええ、どうしても気になるんです…」
風に揺れる漆黒の髪、鈴魅奈と同じ透き通った瞳に、どんな想いもたちまち見抜かれてしまう。この世のものとは思えない程の肌の白さ。彼女が目の前にいるだけで、時間が止ってしまいそうだ。
僕は慌てて頭を左右に振ると、刀を手に取った。刀を構えて桜の木に近づいた時、不意に天女が近づいてきた。
「佐伯さん」
「はっ、はい!」
思わず硬直した。
「あら、緊張しなくて良いのよ」
「いえ、何でもないっす!」
「あたしを見てて下さい…」
「えっ?」
そう言うと急に天女は身を翻し、辺りの桜の枝の間を花びらと共に舞い始めた。一体、何のつもりなのだろうか? 僕を慰めてくれるつもりなのか?
長い黒髪、白い小袖、衣にかけられている赤い帯が、そよ風の中を流れた。それは確かに、この世のものならぬ天女の舞いだった。
彼女は微笑みながら、花の間を舞い遊ぶ。飛び上がったかと思うと、今度は飛び降下する。空の雲さえ、その舞いのために存在しているかのようだ。あまりの優美さに周囲の桜さえも色を失って見えた。
天女はわざわざ舞いを見せるために来たのだろうか? 待てよ…そうじゃない。よくよく注意して見ると、風の動きと一緒に舞っている。僕に微妙な風の変化を教えてくれているのだ。
慌てて刀を手に持って構えた。その途端、天女の思念波が届いてきた。
『自分の周囲に流れている、風の動きを感じるのです』
「風の動き?」
じっと目を閉じ、周囲を流れる風に意識をゆだねる。
「…」
やがてどこからか、心臓の音とともに、サラサラと川の流れのような音が聞こえてきた。ドクン、ドクン、と規則正しい鼓動の音も聞こえる。その音の周囲に流れる川の音。ある時はそれは激しく、ある時は優しく、体の周りに幾重にも重なりあった無数の川が見える。天女の羽衣のように薄い透明な無数の川、これが風の流れの正体なのか?
「さあ、その流れにそって動いてごらんなさい」
言われるがままに、刀をその川の動きに合せた。すると、自然にそれは川と川の間を舞っているような形になった。
「これが…風の流れ?」
再び目を開けた時、目の前には無数の花びらが散っている。刀を静かに横に流す。
「そうか…斬ろうと思うから駄目なんだ」
自分で無駄な風を起こすから、花びらは逃げる。流れに逆らわず一緒になる事。
何も考えず、心を空しくして、自然に刀を流してみた。すると、目の前の桜は次々と二つになってゆく。
「斬れた! 斬れたぞ!」
言いようのない感動が全身を貫いた。風の流れを読む事ができたのだ。
「お見事…」
天女が優しく見下ろしていた。
「とうとう風を読む事ができましたね。やはりあなたにも同じ血が流れているようです」
「えっ?」
「その昔、あの桜の下で修業をしていたのは他でもない、善界だったのです」
やはり、善界もこの異次元に来ていたとは。
「吉野天女、助けてくれて有難う」
「あら、私はあなたを慰めるため、ただ舞ってみただけですわ」
天女はそう言って微笑むと、静かに目の前に舞い降りてきた。
「では、そろそろ詰めといきましょうか」
「新しい術ですか?」
「ええ。少し下がってて下さい」
天女はその場に座り込むと、そのまま地面に右手をついた。続いて奇妙な呪文がその形の良い口から流れ出た。やがて目の前の地面がいっせいに光り輝き始めた。青白い神秘的な炎が周囲にほとばしり、不気味な音が地の底から響き始めた。天女は両手を組んだ。
「鬼獣の魂よ、今、我に力を与え給え。願わくばその霊力を、助けを要するものに与え給え」
再び右手が地面におかれた。
「シュラー、ヴァスティの名において命ずる!」
「!」
「い出よ、風爆鬼!」
「クワアアア!」
突然、鬼の叫びのような叫び聞こえ、激しい大型の竜巻きが目の前に発生した! 身を踊らすように現れたそれは、そのまま頭上をどんどん上がっていき、遥か上空にまで達した。竜巻きのために周囲の桜たちも風になびき、いっせいに花びらを散らし始めた。それと共に砂嵐も発生し、一気に視界が悪くなった。
何て風圧だ! まるで風が生き物のようだ。
じっとしていると、そのまま吹き飛ばされそうだ。
「な、何なんですか、こりゃ!」
僕は風圧に必死で耐えながら言った。
「獣術の中でも、鬼を自分の下僕にする術があります。風爆鬼とは風を操る鬼、さあ、この鬼をあなたの下僕とするのです!」
「そ、そんな事言っても、どうすりゃあいいんですか!」
「知れた事、戦って勝つしかないでしょう?」
「ええっ、どうしたら、勝てるんですか?」
「さっきの修業を思い出すのです!」
そう言っている間にも、風爆鬼は猛烈な勢いで目の前に迫ってきた。あの竜巻きに飲み込まれたら最後だ。
「このまま放っておくと、さらに竜巻きは大きくなります!」
「くそ!」
思いきって刀を手に取り、風爆鬼の前でかまえた。いちかばちかだ!
「でやっ!」
叫び声とともに刀を竜巻きに振り下ろす!
バキッ!
振り降ろされた刀が弾ける。目の前で火花が散り、カミソリのようになった竜巻きが服を切り裂いた。
「うわああ!」
血しぶきが竜巻きと一緒に舞い上がり、頭上を赤く染める。やばいぞ光司!
「もっと間合いを取って、切り刻まれてしまうわ!」
天女の声と同時に、大きくジャンプして何とか竜巻きから逃れた。そのまま後方へとダッシュし、間合いを取る。
何て風圧だ! 服が切り刻まれるなんて。
そう考えている間にも、竜巻きはまた近づいてくる。落ち着け!
じっと目を閉じて、精神を集中させる。大事なのは集中する事だ。
「…」
やがて、意識の視界の中に、物凄い量の川が流れ始めた。巨大な川が渦を巻いて目の前に迫る。その渦巻きは幾つもの小さな川の集りでできており、一つ一つの川は互いに反対向きに流れているのが見えた。
全部が全部、風圧の強いところばかりではないはずだ。必ずどこかに弱い部分がある。
川の流れに精神の目を乗せ、流れにそって『水源』を辿って見る。どこか流れの出発点があるはずだ…。そこを叩けば回転は弱まるはず。
勘は当たっていた。風爆鬼のもろい部分が見えてきた。
「よし!」
もう一度、刀を頭上にかざし、竜巻きを待ち構える。
「もう後がないわ!」
「キュウオオオ!」
唸り声と共に風爆鬼が近づいてきた。
「今だ!」
竜巻きがそばに寄ったと同時に、姿勢を変えて刀を地中に叩き込んだ。土中にはまった刀が鈍い音を立てる。
「上が駄目なら!」
まるでゴルフのスゥイングをするかのように、そのまま刀を流す。風爆鬼が目と鼻の先に迫った時、そのまますくい上げるようにして、土中から刀を飛び出させた。
「下からだ、どうだー!」
キュン!
刀が竜巻きを切り裂く音が響いた。真っ赤な火花が散る。そして短い金属音。
下から上へと斬り上げられた風爆鬼は回転の安定を失い、たちまち目茶苦茶に暴走しだした。竜巻きの中心に割れ目が走ったのが見え、僕はそこにすかさず刀を投げ込んだ。
竜巻きの内部からは鬼の悲鳴が聞こえ、回転が次第に弱まってきた。
「今よ、取り押さえて!」
夢中で鬼に飛びかかり、フットボールのように右手で中心部を押さえ込んだ。暫くは回転盤に乗せられたように周囲がぐるぐると回ったが、やがて鬼は力尽きたのか、そのままピタリと停止してしまった。
後には砂煙だけが舞い上がり、再び吉野山の静けさが戻ってきた。勝ったのだ。
「や、やったぁ!」
改めて捕まえた鬼をよく見て見ると、それは思ったよりも小さく、直径が六十センチくらいの独楽のような形をしていた。昔、正月などで回して遊んだ独楽である。
しかしその体は、ぶ厚く頑丈な鉄の甲羅に覆われており、重量だけはもの凄かった。
「こんなに小さいのか? 随分、可愛い鬼だなあ」
「あなたが睨んだ通り、風爆鬼は独楽と同じ原理で回転します。だから下からバランスを崩されたら弱いのです」
「これが本当に鬼なの?」
「顔の中央を見て下さい、ちゃんと鬼の面があるでしょう?」
そう言われて見て見ると、コマの中央には恐ろしげな顔をした鬼の面があった。鋭い牙がむき出しになっており、京都で戦った数々の鬼を思い出した。
「さあ、早く血の契約をすませて下さい。鬼のが死んでしまいますよ」
「どうするんです?」
「そのまま手を、鬼の顔にあてるのです」
右手を鬼の顔にあてがう。その途端、水蒸気のような煙が立ち上り始めた。右手に激痛が走り、腕の中まで何かが侵入してきたような気がした。
「あちちち!」
「我慢して、鬼があなたの生気を吸収して復活しているのです。そうした場合、主人はあなたとなります」
やがて鬼の姿も、煙と共に右腕の中に吸い込まれていった。不思議な光景だった。
「次からはあなたが鬼を召喚するのです。私の使っていた鬼、うまく使って下さいな」
「はい」
「ふふ、それにしても、随分ひどい有様ですわね」
そう言われて、辺りを見回してみた。あちこちの地面はめくれ上がり、桜の根までが地中から飛び出しているところもあった。酷い自然破壊だ。
天女は別に怒った様子でもなく、安心したような顔で目の前に降りてきた。じっと僕をみつめる表情が、何かを予感させた。
「佐伯さん…」
「はい」
「これでお別れですね」
「あ…ええ」
分ってはいた事だったが、いざ言われるとうろたえた。
「あなたは風爆鬼を会得しました。これでここでの修業は終わりです」
「その、まだ心の準備が! それに…」
言葉の代りに、微かに頬が赤くなった。僕のほのかな想いを天女に悟られてしまっただろうか?
「佐伯さん、下界ではあなたを待っている人たちがたくさんいます。ことだまも、きっとあなたが助けに来てくれるのを待っているでしょう」
「あっ、はい」
「帰るべきところに帰るのです。ここはあなたがいるべき所ではありません」
そんな事は、分っている…。
天女と並んでもと来た道を歩いた。道の両端に並んだ桜たちが、まるでお別れを言っているかのように風に揺れている。白い花びら、桃色の花びら、良くは知らないが、桜にも色々と種類があるようだ。
桜の花びらが散るのを見ていると、自分の中でも何かが散って行くような気がした。
ここはいつまでも美しい桜の園なのだ。永久に変わらないでいて欲しい。天女と一緒に…。
「佐伯さん、戻られたらことだまをお願いしますね」
「ええ。分ってますとも」
「この刀をお持ち下さい」
天女がさっきの刀を鞘に入れ、目の前に差し出した。
「あなたとの出会いの記念です」
「ありがとう」
ぎこちない手つきで、刀を受け取った。
「その刀の名は風神丸と言います」
「風神丸か、かっこいい名前ですね」
再びお寺の門をくぐり、境内の中を歩く。真っ暗な本堂に入ると、八角円堂が僕を待っていたかのように、ひっそりと佇んでいた。
「ここに入るのですか?」
「この円堂は、外部の干渉なく、他の場所に移動するためのものなのです。鈴魅奈やことだまも、皆なここから移動して行きました」
「次元移動装置だったのか!」
「移動先は私が決めます。さあ、乗って」
天女はそう言うと、円堂の扉を静かに開けた。
本当は、言う事は色々とあるはずだったが、いざとなると何も出てこない。天女の優しく微笑んだような、少し寂しげな表情に、僕の心がゆらりと揺れた。時間も空間も、ゆらゆら揺れ動く。それは揺り篭のように優しく…そしてもの悲しかった。
桜色の唇が微かに動いた。
「佐伯さん」
「はい」
「お元気でね」
頬に優しい感触が伝わった。
「私はいつでも見守っていますよ」
天女は静かに離れて行った。
「さよなら…」
そう呟くと、想いを振り切るようにして円堂の中に入った。扉を締め、軽く深呼吸する。
刀を抱えたまま、そのまま床の上に座り込んだ。
今は、威追を倒す事だけを考えるんだ!
少しして、円堂の外から、天女の呪文が聞こえた。途端に周囲の木の壁が様々な色で輝き始め、グルグルと回転し始めた。下手に動けなくするためなのだろうか? 重力に押されて床の上に突っ伏した。
激しい閃光が全身を包み、白い闇が視界を覆う。
気を失う瞬間、天女のさようなら佐伯さん、と言う声が聞こえたような気がした。
|
|