夜の火川神社、後藤氏に留守番をいいつけられた鈴魅亜は、まだ修理の終わってない社務所の中で皆なの帰りを待っていた。風でざわめく周囲の木々、鈴魅亜にはそれが悪魔の囁きのように思えた。
じっと耳をすましていると、何かが忍び寄って来るような気がして、その細い肩をすくめた。ギュッと膝元の胡蝶を抱きしめ、ボンヤリと天井を見つめ、一人ため息をついた。
『どうしたの?』
胡蝶が鈴魅亜を見上げて微笑む。
「ん、何でもないわ」
茶色の髪の毛が微かに揺れ、透き通るような瞳が遠くを見つめた。
目を閉じたまま、白い指先で自分の髪に手櫛をかける。その度に腰まで伸びた長い髪が揺れた。
『なにを考えてるの・昔のこと?』
赤い瞳が微かに曇った。
昔の事…。
その一言が、心の中に波紋のように広がる。思い出したくない過去のいまわしい記憶。
前世の幸せだった頃の自分の姿。できたらもう一度、あの頃に戻りたい。家族と幸せに暮していたあの頃に。
少女は胡蝶を抱き上げた。
「どうして…分るの?」
『ときどき・あなたの・泣く声が聞こえるの』
「泣く声?」
『魂の・行き場が・ないって・泣いてるわ』
「そうね…」
鈴魅亜は微かに微笑んだ。
「確かにあたしはこの世の者ではないわ。だって一度は死んじゃった身だもの」
『どうして?』
「殺されたからよ、悪魔に」
胡蝶は首をかしげる。
『悪魔?』
「そっか、今の胡蝶には分かんないよね」
そう言うと鈴魅亜はそっと立ち上がり、社務所から奥の座敷へと向った。威追が攻撃した時に空いた穴からは、秋の冷たい風が入ってくる。座敷へ入り、小袖の上に上衣をかけると、窓から空の月を仰ぎ見た。辺りを照す月光、あの時もこんな月の綺麗な夜だった。
鈴魅亜の昔の記憶と言うのは、まだ幸せだった頃のほんの数年間の間しかない。後の記憶は全て吉野山での事だけだ。
あの時の月も綺麗だった、それもぞっとする程。
おぼろげに顔に浮かんでくる優しかった両親の顔、そして大好きだった兄、泣くといつも優しく抱きしめてくれた幼い頃の甘い記憶。周囲にいた人たちは皆、自分に優しかった。自分に出会うと、いつも微笑んでくれた。こんな幸せが永遠に続くと思っていた。
あの時は毎日、笑っていたような気がする。
本当はその優しさが、自分を鬼のいけにえにするためのものとは知らずに。
ある日、鈴魅亜が十六歳になった時のお祝いとして、村で大きな祭があった。村人が全員揃い、祭は盛大にとり行なわれた。皆が優しい笑顔で自分の事を祝ってくれたのだ。鈴魅亜は幸せだった。
そして、その祭の儀式が終わった後、突然、両親に真っ白な着物を着せられた。「この方が綺麗だから」と。
村長(むらおさ)に手を引っ張られ、雑草しかない荒野を歩かされる。空を見上げると、大きな月が上っており、その光に自分が照された時、村長は満足気な顔をした。
「美しい娘だ。これだけの子なら今年も村は安泰だな」
嬉しさに興奮しきっていた鈴魅亜は、それが何の事か分らず、ただ言われるままに歩いた。
「村長さん、もう疲れたわ」
「もう少しだよ。もう少し行ったらいい事が待ってるからね。ちゃんと我慢できたらご褒美を上げよう」
村長は優しさを満面に浮かべて、鈴魅亜に言い聞かせる。
「ほんと、どんなご褒美?」
「お前をびっくりさせたいからねぇ、内諸にしとくよ」
甘い言葉につい嬉しくなり、飛び跳ねながら大人たちの後について行った。本当はその時、村長がニタリと笑った事も知らずに。
やがて、小高い丘の前に一つの大きなほら穴が見えてきた。村長が指さして言う。
「ほら、あの中にご褒美があるんだよ」
「一体、何?」
「ふふふ、一緒に入ろうね」
そしてほら穴の中に入った途端、突然、村長の表情が一変した。そして何も見えないほら穴の中に自分を突き飛ばした。
「きゃあ!」
薄暗いほら穴の中で思いっきり転び、着物まで泥だらけになった。
やがて、泣きながら身を起こすと、ロウソクの火に照された、大人達の醜く歪んだ顔がそこにあった。
「ククク、お前はもう逃げられないんだよ」
「ここで鬼神様のいけにえとなるのさ」
村長は有無を言わさず、自分の体を縛り上げ、そして足に鎖をつなげた。冷たい鎖に激しく締め上げられ、真っ赤な血が滲んだ。
「ふふふ、綺麗な血だ」
「もうすぐ鬼神様が迎えに来るよ。これが最後のご褒美だ」
「いやあ、助けて!」
真っ暗なほら穴の中に、泣き叫ぶ自分を残して村長たちは去って行った。
嘘だわ、こんな事、きっと嘘…。
泣きじゃくりながらそう思った時、鈴魅亜は思い出した。村の中で年に一人ずつ、自分と同じぐらいの年の子供が、いつの間にかいなくなっていた事を。他の子たちも生け贄にされたのだ。
やがて暗闇に目が馴れてくると、地面に白い物が幾つも転がっているのが見える。
手に取ってじっくりと見る。それが人間の頭がい骨と分って、悲鳴を上げて放り投げた。
村の子供たちのだ…。
もう誰にも聞こえない。誰も助けに来てはくれない。
それが分った時、果てしない絶望に打ちひしがれた。体の芯まで凍らせてしまうような深く冷たい絶望。
まだ子供の自分に、鎖をたち切るような力はとてもなかった。他の子たちもこんな絶望を味わいながら死んで行ったのだろうか? そう思うと余計に涙が溢れ、白い頬に伝わった。
「シャアア!」
どこからか聞こえてくる、ひどくしゃがれた蛇のような声、段々とその声は近づいてきた。鬼神が自分の血の匂いを嗅ぎつけてきたのだろうか? しゃがれた声に身をすくめた。
そして、目の前には巨大な鬼が姿を現わす。月光にその姿はシルエットとなっていたが、暗闇に凶悪な二つの目が、らんらんと輝いているのが分った。大きく裂けた口元からは唾液が水のように流れ落ち、両方の手から伸びた長い爪が自分の柔らかな皮膚を引き裂く事が容易に分った。あまりの恐ろしい姿に後ずさりした。
そして、鬼の後ろには長身の一人の男が立っていた。瞳は真っ赤に輝き、その口許からは残忍な笑いが洩れていた。
「今度はこの娘か、ククク」
「た、助けて、お願い」
少女の哀願に、男は意外そうな表情を見せる。
「助けてだと? ククク、無理な相談だな、せいぜい苦しんで死ぬがいい」
「いや、お願い、村に帰して!」
「無駄な事だ、今更、村に帰っても、お前の仲間は誰もいない」
「誰もいない、どういう事!」
「お前の肉親や回りの者たちは、皆なここにいる飢鬼のように変わり果てておるわ。今更、戻ったところで同じ事」
「そんな、嘘よ!」
「ククク、自分の身の回りの者が次々と鬼に変わって行くのが分らなかったようだな。哀れな小娘だ」
爪が振り上げられ、一気に胴体を貫く。
「ぐぅ…」
目の前に火花が散った。この世のものとは思えない程の、美しい命の火花。それが消えると同時に、段々と視界に霞がかってくる。ろくに声を上げる事もできなかった。悔しい…こんなところで死にたくない。誰か、誰か助けて。
その時だった。おぼろげな意識の中で誰かの声が聞こえたのは。
「威追、その辺でやめなさい」
「フン、誰かと思ったら吉野天女か。いや、ヴァスティと言った方がいいかな? こんなところまで邪魔しに来るとはな」
「その子はまだ生きています。速くその飢鬼の爪をどかせなさい。さもないと」
「さもないと?」
「今度は私が相手ですよ」
暫くの沈黙が続いた。
「フン、今日のところはこれで辞めるとしよう。しかし天女、お前もきっとそのうち始末してやる」
「威追、お前はその自信故に滅びる日が来るでしょう」
「ククク、我は絶対の存在、そんな事はありえない。飢鬼よ、帰るぞ!」
「 シャアアアア!」
あっという間の出来事だった。天女は無言のまま、ほら穴の中に入って来ると、倒れている鈴魅亜に近づき、そしてゆっくりと抱え上げた。優しい香りがした。
「もう既に虫の息ですね、でも死んではいません。これだったら、人間には戻れなくても、せめて…」
天女はそう言うと、鈴魅亜を両腕に抱えたまま、青白い月光の中を歩き去った。
「…」
気が付いた時、鈴魅亜は自分が桜の中で寝ているのに気が付いた。辺り一面の桜…。
そして、傍らには吉野天女がいた。今と全く変わらない微笑みを浮かべて。鈴魅亜は時間も止ってしまいそうな気がするくらい、その天女の美しさにハッとした。
「気がつきましたか?」
鈴魅亜の心の中に、桜の花びらが舞った。
「あの、あたしはどうしたんでしょう…か」
茫然としながらも、鈴魅亜は何とか言葉を発した。
「貴女は今日から生まれ変わったのです。妖精として」
「妖精?」
微かに頷く天女、漆黒の美しい髪が風に揺れた。そして、その天女の傍らには自分より小さな女の子が。あどけない表情、キョトンとした大きな両目で自分を見ている。
「お姉ちゃん、目が綺麗でちゅ」
「えっ、目が?」
「髪もとっても綺麗でちゅ」
鈴魅亜は小さな境内の中に入り、水面に自分の姿を映してみた。
「あっ、どうして? 目が赤いし、髪も茶色だわ」
「あなたは妖精として生まれ変わり、髪や目の色まで変化したのです。今までの悪い夢を心の中から消し去るためです」
「消し去るため?」
「あなたは、もう生まれ変わったのだから、前の姿とは違うのです。あなたの生はここから新しく始まるのです」
「新しいあたし、か…」
こんな姿は想像もしてなかった事だが、生まれ変わったその姿に、まんざらではなかった。むしろ、生前の自分からは考えられないほど美しい。日差しを反射して淡い光を発する茶色の髪、どこまでも透き通った、宝石のような赤い瞳。そうした姿に、自分自身が吸い込まれてしまいそうだった。
死んでみて良かったかな…。
そんな事をふと考えたりして、自分で苦笑した。だが、あの威追の事は忘れない。いくら天女に新しい姿にされたと言っても、両親や兄、親しくしていた人たちの恨みは忘れない。絶対に!
そんな自分の表情が水面に映ったためだろうか? 天女はおだやかな口調で言った。
「復讐のために生きるほど虚しいものはありません。貴女の敵は、然るべき者が討つ事でしょう」
「然るべき者?」
「ええ。まだまだ時間はかかりますが、神々に選ばれた者が必ず、貴女たちの敵を討つ事でしょう。あなたは復讐よりも、自分の事を考えねばなりません。ここにいる、ことだまにしても、貴女のような目に遭ってここに来たのですよ」
「ここで安穏と暮せと言うの? そりゃあ、そこにいる小さな女の子はそれでいいでしょうよ、だけどあたしは…」
「いつかその者がここに訪れたら、きっと貴女や、ことだまの手助けを必要とするでしょう。その時こそ、下界に降りて行きなさい。それまではここで準備をするのです」
「準備?」
「ええ、覚える事はたくさん、ありますよ」
「あたしは、他人の手を借りず、自分で敵を討ちたいわ」
「気持ちは分ります。しかし、貴女の敵は私たちの敵でもあります。相手はとてつもなく強大です。一人や二人か集ったところで、到底かないませんよ」
「どうしてそんな事が分るの? 貴女は一体、誰なの?」
「うふふ、それは秘密です。教えて上げない」
天女は子供のように微笑むと、鈴魅亜の質問を軽く受け流した。その思いもよらぬ仕草に鈴魅亜の胸がキュンとなった。
この人、なんて綺麗で可愛いんだろ…。
そして、その日から鈴魅亜は妖精として様々な教育や訓練を受けた。基本的な兵法や妖術は天女に、様々な語学や教養はことだまから受けた。ことだまは、さすがに言葉の妖精として生まれ変わっただけの事はある。この子の方が遥かに多くの言葉を解し、全ての事を知っていた。
やがて、長い年月が経った後、とうとうその然るべき者が現れた。鈴魅亜は、とてつもない力強い猛者を想像していたのだが、期待外れだった。ちょっと下界を探せばどこにでもいそうな、そんなタイプの若者だ。おまけに片腕を落とされていて、見るも無残な姿だった。あの佐伯光司という人。
「本当にこの人が?」
おそらく、本人は気付いていないのだろうが、少なくとも鈴魅亜は始め、彼を見た時そう思った。どっちかといえばと頼りない感じである。
ことだまの事を心配しているのは分るが、すぐに泣いたり喚いたりして、男のくせにもう少し、しっかりしろと言いたくなってくる。もしかして自分にはまだ女としての部分が残っているのだろうか? できたらもう少し、毅然としたカッコイイ人に来て欲しかったなあ…。あんなメソメソした男ではなく。
それとも、既に妖精となった自分は、人間に対して何らかの嫉妬心があるのかも知れない。あの佐伯光司、自分が既に失ってしまったものを持っているのかも。
「人間くさいよね…」
そう、あまりに人間くさいのだ。佐伯光司も、あの超常現象調査会の連中も。そんな連中に呆れながらも、自分はついて来たのだ。
「人間…かぁ」
胡蝶を膝元に抱いたまま、鈴魅亜はもう一度、ため息をついた。そして、空の月を見上げた。
その時だった。
参道の大鳥居のところにいる狛犬たちが騒ぎ出した。
「グルルルル!」
虎かライオンのような唸り声が聞こえ、二頭の狛犬は次々と、見る者を圧倒する獅子へと変貌をとげて行く。神々しい光が全身から満ち溢れ、それが周囲の、まがまがしさを払い退けたかのように思われた。スパークした光が辺りに飛び散り、眩しさに目を覆った。獅子たちが復活したのだ。
「あなたたちは、炎獅子に電獅子?」
「天女の妖精、鈴魅亜よ。私の背中に乗るがいい」
「乗れって言っても、どこに行くの?」
「斑鳩寺だ、やっと威追たちの気配が現れよったわい! 時間はない、行くぞ!」
「わ、分ったわ、待ってよ」
鈴魅亜は仕方なく、胡蝶を膝から降ろした。下手に連れて行って、戦う力のない胡蝶に怪我でもされたら困る。そうなったら自分の責任だ。宿直の神職に急いで胡蝶を託した。
「御免なさい。この子をお願いします!」
「ああ、いいですけど?」
びっくりしている神職を残し、鈴魅亜は電獅子の背中に飛び乗った。
「行くぞ!」
「グオオ!」
二頭の獅子が夜空に吠えた。そして、地面に蹴りを入れると、あっという間に遥か上空まで飛び上がった。
「ひゃあ、凄い! 待ってなさいよ、威追、今行くから!」
冷たい秋風が鈴魅亜の長い茶色い髪をなびかせた。
その頃、調査会の面々はとうとう夢殿の前まで近づいていた。石畳の上を慎重に進む。クワィロゥはここにあるのだろうか。しかし、それを破壊すると周囲にどんな影響を及ぼすのかは、見当もつかなかった。四脚門の前まで来ると、一度、足を止めた。
「いよいよ東院の境内ですね」
門の向こうを見ると、舎利殿と呼ばれる回廊が見えていた。問題の夢殿はその真ん中に位置しているのだ。例の火災事件に巻き込まれた人たちはここを歩いていたらしい。
「さて、どうしますか?」
「そうですね。林田兄妹は我々の周囲に結界を張って下さい。いつ体に火がつくか分りませんからね」
後藤氏が後ろで言った。それは充分ありうることだ。
林田兄妹に結界を張らせ、四脚門からゆっくりと境内に入った。その時、夢殿の上に人影が映った。あの悪魔だ!
「威追!」
『ククク、小僧、やっと来たか。随分待ちわびたぞ。俺の土蜘蛛はどうだ?』
「きさま、卑怯な手を使いやがって、胡蝶の記憶を戻せ!」
『それはできん相談だ。それよりも自分の身を心配するんだな』
「ことだまはどうした!」
『この夢殿の中にいる』
「さっさと返せ!」
『愚かな。そんなにこの赤ん坊が可愛いか。返してやるから回廊を出て、夢殿の前まで来い』
「佐伯さん、きっと罠ですよ!」
林田が叫ぶ。しかし他に方法がない。
「分ってるよ。何かあったら助けて下さい」
回廊から慎重に足を踏み出す。だが、足を一歩出した時、思わぬ罠が待ち構えていた。不意に背後に立ち並んでいた回廊の柱が、次々と折れ始めたのだ。
「あっ!」
ズズン! という地響が轟いた。回廊の屋根が地面の上に落ち、後ろにいた仲間は閉じ込められてしまったのだ。だが、まりちゃんだけは屋根には捕まらず、空中に飛び出した。
「しまった、皆なを閉じ込めるためだったのか!」
『ほんの数分の時間でいいからな、黒魔理(ブラックマリー)よ、あの生意気なヒトガタの相手をしてやれ!』
その声と共に、夢殿の中からブラックマリーが飛び出してきた。そのまま空中にいたまりちゃんと対峙する。黒い悪魔は余裕の表情だった。
『性懲りもなく、また闘うつもり? まりこ』
『もう絶対に、あなたには負けないわ!』
『よほど死に急ぎたいのね』
再び二人の間で火花が飛び散る。両者の全身がサイキックエネルギーに包まれていくのが分った。またあの壮絶なバトルが始まるのか?
『佐伯、お前の欲しがっていた左腕と赤ん坊だ』
「ことだま!」
夢殿の開いた扉から、ことだまが飛び出してきた。手にはガラスのような物でできた細長い容器を持っている。中に左腕が入っているのが見えた。
「ひ、左腕だ!」
一瞬、我を忘れて走り寄った。これさえあれば善界の弓が!
夢中で走ってくることだまを受け止めた。左腕を抱きしめ、しゃくり上げることだまを見て、少しほっとした。その小さな頭にポンと手を乗せた。
「光司!」
「偉いぞ。よく我慢したな」
「腕、ちゃんと守ったでちゅ」
「有難うよ」
取り敢えず、この子を安全な場所に。そう思った時、また思わぬ落とし穴があるのに気が付かなかった。不意に足下の砂利が波うち始めたかと思うと、急速に回転を始めたのだ。
「うわああ!」
「馬鹿め、重力結界にかかったな!」
「重力結界!」
「お前をなぜここに呼んだか教えてやろう。元から俺は、お前の価値のない左腕や、そんな子供の事はどうでも良かったのだ」
「どういう事だ!」
「ふふふ、その重力結界にはまったら、二度と出てくる事はできん。最後まで重力をかけ続けるとどうなるか? お前の体は圧縮されて舎利と化すのよ」
「舎利だって!」
「そうだ。あの善界のようにな。お前が舎利になった後、そのエネルギーは阿修羅のために使ってやろう。偉大なる闇の帝王のためにな、その赤ん坊とともに舎利と化すがいい!」
『そうはさせない!』
頭上にいたまりちゃんが、結界を壊そうと降下してきた。だが、その前にブラックマリーが立ち塞がる。
『あなたの相手はあたしじゃなかったの?』
ズガッ!
打撃の音が響いた。強烈なパンチがまりちゃんを襲う。不意をつかれたまりちゃんは、身を折り曲げたまま、塀の中に突っ込んで行った。
「まりちゃん!」
『ふふ、どうしたの? もうグロッキーなの?』
ブラックマリーは塀に埋っていたまりちゃんを、片手で掴んで引き摺り出した。胸倉を掴んだまま、目の高さに持ち上げる。
『前より弱くなったかな?』
『それはどうかしら』
不意にまりちゃんの目が開いた。と同時に膝蹴りが飛ぶ。ブラックマリーはうっ、と唸ったまま、地面に落ちた。地上に降りた後、再び両者は睨み合う。
『行くわよ!』
不意に二人は、互いの両手を鷲掴みにし、力比べを始めた。ギギギ…と腕が軋んでいるのだろうか? 両者の力がまともにぶつかり合い、再び空間が歪み出す。激しい闘気に二人の髪が宙に浮かび上がった。
『くっ!』
『こいつ!』
あまりの力の競り合いに、周囲の地面が陥没し始めた。ボコッ! と音を立てて地面が沈下して行く。
「まりちゃん!」
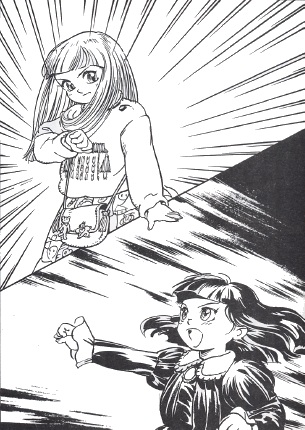 『ここで引いたら、人形がすたるわ!』
『ここで引いたら、人形がすたるわ!』
『こっちだって!』
二人が戦っている間にも、結界の重力はどんどん大きくなってくる。あまりの圧力で、骨が折れてしまいそうだ。信じがたい程の不快感が内蔵をかけ巡っていた。
「ちくしょう、こうなったら!」
右手を結界の中心に向けた。
「い出よ、風爆鬼!」
クワアアア! という獣鬼の叫び声とともに、竜巻きが発生した。あっという間に周囲の砂利が巻き上げられ、それと共に全身にのしかかっていた重力も竜巻きに吸い上げられた。
「やったぜ、結界を巻き込んで行くぞ!」
ドン!
重たい重力の崩壊する音が響くと同時に、足下からも砂利が吹き出し、体ごと円の外に弾き出された。きりもみ状態になって回転し、地面に墜落する。砂利が口や目の中に入り、暫く体勢をたて直すのに時間がかかる。体中のあちこちが痛んだ。
「ことだまは?」
慌てて土煙が舞う中を目をこらすと、回廊の屋根に持たれて気絶しているようだった。わずかばかり安心した。
突然の結界の崩壊に、威追の表情が険しくなる。
『くそっ。もうひと息というところで!』
「残念だったな威追、僕もことだまも、もう阿修羅の強化には使えないぞ!」
『どうやら天女のもとで、少しは修業してきたようだな。試してやろう』
威追は再び長剣をかまえ、瞬時に移動してきて僕の目の前に立った。あの奈良公園の亜空間の時と同じだ。
よほど相手をいたぶるのが好きらしい。悪趣味な奴だ…。
『小僧、どうやら風の修業をしたようだな。成果を見せてみろ!』
威追が身を翻し、飛びかかってきた。長剣がギラリと輝き、唸りを上げて飛んできた。間一髪でそれをかわし、後ろへと飛び返る。耳元で風が唸った。
落ち着くんだ。きっと見えるはずだ。奴の早い動きだって…。
じっと目を閉じ、精神を集中させる。
やがて微妙な風の変化が意識の中に現れる。風の羽衣が幾重にも重なっているのが見えた。落ち着いて見るんだ。
ドシュ!
長剣が肉を切り裂く、生々しい音が響いた。一体、どうしたのだろうか? 目を開けて見ると右足を斬られていた。真っ赤な血が辺りに飛び散り、服を染めていく。
「うわああ!」
『ふふ、小僧、そんな生易しい修業で本当に風を会得できたと思っていたのか? 愚かな奴だ』
「な、なぜだ。なぜ風の動きが見えない!」
『教えてやろう。修業をしたお前になぜ、俺の動きが見えないか。幾らお前が風を感知したところで、それより俺の動きの方が早かったら意味がないという事だ』
「そ、そんな…」
『諦めろ。運動能力の違いだ、そんな小手先の修業が何になる!』
嘲笑とともに、稲妻のような蹴りを頭に喰らう。弾かれたように、再び砂利の上に投げ出された。這って逃げようとするところを、堅いブーツがのしかかる。仕返しをするどころか、また同じ事になってしまった。
「ち、ちくしょう!」
脳裏に天女と鈴魅亜の顔が浮かんでくる。こんなはずじゃなかった、あの修業は何のためだったのか。
『悔しいか佐伯、悔しかったら立ち上がって見ろ!』
「ぐぐ…」
『ふふ、今一度、重力結界を発生させてやろう。あの日本人形のヒトガタも、今頃はのんびりとしているだろうな。くくく…』
だが、威追のそうした余裕も長くは続かなかった。遠くから強力な何者かが近づいてくるのを感じたからである。周囲に張り巡らされていた悪魔の気がそれを敏感にキャッチしていた。
『どうやら援軍が近づいているようだな。だが所詮は小娘と犬が二匹か』
やがて、ヒュウオオオ! と風の唸る音が東院の境内に響き渡った。その風によって周囲の木々はざわめき、唸る風が獣神の到来を告げていた。
「むっ!」
次に何が起こるか、それを察知するのは威追の方が早かった。威追は踏みつけていた足をどけると、ものすごい跳躍力で地面に沈んでいる回廊の屋根に飛び乗った。その後を蛇が這うようにして電獅子の稲妻が襲う。雷撃に周囲の砂利が吹き飛び、境内中に飛び散った。
「グオオオオ!」
獣神の砲哮が夜空にこだまする。巨大な口をカッ! と開き、らんらんと光る金色の目が相手を威圧するかのようだ。風に乗って金色の粉が流れる。
鈴魅亜を乗せた電獅子は目の前に降り立ち、炎獅子の方はまりちゃんと、取っ組み合いをしていたブラックマリーに火炎放射を浴びせた。
『ちっ!』
その刹那、ブラックマリーは盾のようなバリヤーを素速く右腕に形成し、その火炎を跳ね返した。ブラックマリーも再び、威追の隣に移動して邪気のこもった笑いを見せる。
「大丈夫?」
倒れていたところを鈴魅亜に助け起こされた。
「何とか…」
鈴魅亜を降ろした電獅子は、今度はその電撃を回廊の屋根に向けた。
ドドド!
次々と屋根の瓦が吹き飛び、中の木材がむき出しになる。回廊の屋根はそのまま真っ二つとなり、中から閉じ込められていた林田たちが飛び出した。林田兄妹が『潮騒の双剣』をかまえた。
「よくも長い間、閉じ込めてくれたな。威追、覚悟!」
玲子が刀を頭上にかかげたのを、鈴魅亜が止める。
「待って、あたしがやるわ!」
「えっ?」
「お願い。あたしにやらせて」
彼女の真剣なまなざしに、玲子は『潮騒の双剣』を下に降ろした。
鈴魅亜は僕のところに歩み寄り、手を差し出した。
「その風神丸をかして」
「あっ、ああ」
キョトンとした僕から刀を受け取り、鈴魅亜は威追の前に立った。その透き通った赤い瞳は悪魔の紅い両眼を睨む。
「今度はあたしが相手よ」
『小娘、今度は前のようにはいかんぞ』
威追の挑発に対し、鈴魅亜が微かに笑う。
「威追、勝負よ。あたしはこの日を待っていた!」
『面白い、この俺と刃を交えるつもりか。ヴァスティのもとで少しは修業を積んだようだな』
ヴァスティ…もしかして天女の事か?
そう思った刹那、両者は互いの剣を交わしあっていた。キーン! と金属音が響き、それが何度も繰り返された。ハッと思った時には、威追が打ち下ろした剣を鈴魅亜が必死で支えていた。
『どうした、このまま押し潰してやろうか?』
「くっ!」
ジャリッ、という音が響き、刀から火花が散った。鈴魅亜は押し付けられていた刀を器用にスライドさせると、それを一気に威追の胴体めがけて抜いた。力のあてがなくなった威追は、おおっ! と呻きながら前のめりになる。鈴魅亜の刀が威追の胴体を切り裂いていた。真っ赤な血がパッと飛び散った。
『ば、馬鹿な。この俺が!』
「その自信があなたの命取りよ、威追!」
傷ついたその胴体を貫くかのように、刀が真っ直ぐに突き出される。だが、威追はその突き出された刀身を膝で蹴り上げた。
「あっ!」
あっという間に、風神丸が宙に飛び上がる。刀は宙で回転すると、そのまま砂利の上に鈍い音を立てて落ちた。鈴魅亜に焦りの表情が浮かんだ。
『どうした、小娘、刀を拾え』
「えっ?」
『刀を拾ってさっさと来い。くく…本当なら既にお前は死んでいるぞ』
鈴魅亜は数メートル離れた場所にあった刀を拾い、再び構えた。また両者は睨み合う。
不思議な光景だった。どうして威追は手加減をしたのか、普通ならとっくに光術で鈴魅亜を攻撃しているはずだった。
「プライドですよ」
後ろで後藤氏の擦れた声がした。
「プライド?」
「そうです。おそらく、あそこまで威追を追い詰めた者はいなかったんでしょうなぁ。剣でやられたら剣で相手を倒す。それが奴の秘教の使い魔としてのプライドなんでしょう。鈴魅亜が相手にならないほど未熟だったら、さっさと光術を出していたと思いますよ」
再び両者の剣がぶつかる。静寂の中、激しい火花が飛んだ。だが、体格では圧倒的に威追の方が有利だ。その威追の巨大な力を、鈴魅亜は風を受けるかのように受け流していく。威追も力を出し過ぎると隙を突かれると判断したのだろうか。あまり深くは飛び込まないようになってきた。
ゴゥ!
威追が剣を振ると風が巻き起こる。横向きにはらった剣が鈴魅亜の胴体を狙った。ガシッ! という音が響く。斬られたのか?
『こ、小娘…』
「残念でした」
見ると鈴魅亜は横から襲いかかった威追の剣を、腰の脇差しを抜いて受け止めていた。自由になった右手の刀が振り上げられた! 両目がカッ、と開かれる。
「覚悟!」
『ぬぅ!』
だが、そう簡単に威追はやられてはくれなかった。瞬時に身を低くすると、鈴魅亜の懐に入り込み、拳の一撃を腹に叩き込んだ。
「ぐっ!」
身を折り曲げて飛ばされる鈴魅亜に威追が襲いかかる。
「危ない!」
慌てた玲子が『潮騒の双剣』で斬りかかろうとした時、突然、地の底から不気味な声が聞こえてきた。月夜に轟く不気味な声。
『威追よ、その辺でやめておけ。移動するぞ』
『何』
鈴魅亜を真っ二つにしようと、迫っていた威追はピタリとその動きを止めた。地面を見つめたまま眉間に皺を寄せ、歯をギリリと噛んでいる。だが、やがてその命令の声に全てを諦めたのか、剣を鞘に納めた。
『ちっ、仕方がない!』
「威追!」
玲子の『潮騒の双剣』が唸る。だが、威追はその閃光をいとも簡単にかわすと、大きく跳躍して夢殿の屋根に飛び乗った。そして横に並ぶブラックマリー。
『くく、せっかくお前たちを抹殺できるところだったのに、もはや遊んでいる時間はなくなったようだ。今日のところは引くとしよう』
「何だって!」
『佐伯、この次に会う時までは少しは力を蓄えるがいい。くくく…。お前の左腕と赤ん坊は返してやろう。あの方が完全体となった今、もう 用はない』
「完全体だと、まさか!」
『その通りだ。あの方は既に完全な力を持った。もはやお前たちにかまっている暇はない。この次に会う時こそ、皆殺しにしてやろうぞ!』
威追が高らかに笑った時、信じられない事が起こった。遠くの方からズズズズ…と地鳴りが響いて来たかと思うと、足下の地面が揺れ出したのだ。
「じ、地面が揺れてる!」
田村刑事が叫んだ時、さらに揺れは大きくなる。砂利の地面が波うつようにして隆起を始めた。そして、境内の右手の方から何メートルはあろうかという、一本の巨大な腕が砂利を吹き飛ばしながら姿を現わした。
「あれは!」
続いて左手からももう一本の腕が。さらに前後にも巨大な腕は出現した。
大地を揺さぶるゴゴゴゴ…という音はさらに大きくなり、ついには境内に幾つもの亀裂が走った。
「いかん、境内から出るんだ!」
後藤氏の声とともに、四脚門から全員外に飛び出した。石畳の上を走りながら後を振り返った。
境内の建物を全て地に沈め、膨大な量の土砂を宙に吹き上げながら、巨大なる悪神はその完全な姿を現わした。飛び出した岩石が石畳の上にまで落下して来る。それをさけるためにはさらに下がるしかなかった。
一体、奴は何十メートルあるのだろうか? 斑鳩の上空に巨大な三面六臂の邪神が浮かび上がった。そして、空の色もその誕生に呼応するかのように真紅に染まり、暗雲が幾つも上空に群がってきていた。
まりちゃんに折られたはずの腕も、元通りに復元されていた。やはり阿修羅は斑鳩寺に潜んでいたのだ。
「とうとう出やがったな!」
「ああ、ついに首魁が姿を見せやがった!」
「でも、どうしてこんなに早く完全体になったんだ!」
『簡単な事よ、この寺に発生していたクワィロゥのエネルギーを、そのまま阿修羅の神霊に吸収させたのだ。クワィロゥは消滅したが、このまま飛んで移動しても問題はない』
威追の得意そうな説明が頭に響いてきた。
『待ちなさい、阿修羅!』
まりちゃんの声に、阿修羅の巨大な瞳が下に向けられた。
『ヒトガタ、何の用だ』
『胡蝶の、胡蝶の記憶を返しなさい!』
まりちゃんは全身を怒りに震わせ、大声で叫んだ。
『ふふ、愚かな。下らぬ者は、やはり下らぬ事を心配する様だな』
『く、くだらない?』
その言葉を聞いた途端、まりちゃんの全身が青白く輝いた。サイキックエネルギーが爆発したのだ。
『よくも、よくも胡蝶の事を、皆の事を、くだらないとか言ったわね! 許せない、阿修羅、お前だけは絶対に!』
『やめておけ、ヒトガタ。所詮、お前の力には限界がある』
阿修羅が嘲笑した。
『うるさい!』
全身を包んでいたサイキックエネルギーがひときわ輝き始めた。
『お前も鬼芭王のように、ふっ飛ばしてやる!』
ドドドド! とジェット噴射が吹き出す。それはまるでロケットの発射の瞬間を思わせた。おびただしい煙が石畳の上を走り、あっという間に視界をゼロにした。やっと目が見えたかと思うと、青い閃光が斑鳩の空に飛び出して行くのが分った。まりちゃんはそのまま向って行くつもりなのだ。
「行けー、まりちゃん、ぶっ殺せ!」
田村刑事が拳を振り上げて叫ぶ。
まりちゃんは拳をかためると、一気に阿修羅に突っ込んで行った。
『くく、愚かな!』
威追が嘲笑した。
『ダアッ!』
ズドオオンン!
空気を揺るがす、物凄い波動音が伝わってきた。その音に木材でできた建物が身をすくめたように揺れた。物凄い衝撃が空中で走ったのだ。
爆発があった瞬間、阿修羅の全身は暫く煙に包まれていた。しかし、その煙が消えた後の光景を見て、全員が茫然となった。
「ま、まさか」
『渾身の一撃だったはずなのに!』
阿修羅は傷一つ負っていなかったのだ。逆にまりちゃんが弾き飛ばされ、目の前にある大宝蔵殿の方に墜落して行くのが見えた。ドーン! という音とともに、瓦の屋根をぶち破り、木材をまき散らしながら、墜落するまりちゃん。誰もが目を疑った。
「そ、そんな馬鹿な!」
『愚か者め。かつては世界を焼き尽くした我に、そう簡単に太刀打ちできると思っていたのか?もはや完全体になった我に恐れるものはない!我が力、とくと見るがいい!』
その言葉と同時に、阿修羅は右の腕を地表に向けた。その途端、手が向けられた方向の建物が、音を立てて燃え上がり始めた。ゴオオオ!と轟音を立ててそこら辺りが火の海と化した。
「そんな、触ってもいないのに!」
次に阿修羅の左手が別の方向に流れた、その方向からも途端に火の手が上がり、ガス爆発を起こしたのだろうか? 住宅が何軒も吹き飛んだ。木材や瓦屋根が空に舞い上がる。
「な、何て事をしやがる!」
「やめろ〜!」
『くくく、同じ人間が火にまかれて死ぬのをとくと見るがいい!』
「ちくしょう!」
『佐伯光司、然るべき者よ。また会おう、この次はお前たちが我が劫火に飲まるる時ぞ』
阿修羅はそう言うと、全員に一瞥をよこし、頭上にあった暗雲に紛れてそのまま消え去ろうとしていた。興福寺で対決した時と同じように。ズズズ…と低い音が響かせ、消えて行く悪魔。
「ちっくしょう!」
だが、そこにいる誰もが動く事ができなかった。あれほどとてつもない相手とは思っていなかったのだ。一体、どうやってあんな怪物と戦えばいいのだろうか? 破壊力は鬼芭王の比ではなかった。強過ぎる…。
やがて、宝蔵殿に埋もれていたまりちゃんが瓦屋根を吹き飛ばし、外に姿を現わした。誰もが一瞬、ホッとした。
「まりちゃん!」
だが、まりちゃんはそれには応えず。じっと阿修羅の消え行く上空を見つめていた。
大きな両目には何が映っていたのか。悪魔の嘲笑だろうか? それとも胡蝶の記憶の行方か。
『阿修羅、今日は負けたけど。今度は必ず…』
そう言うとまりちゃんは、唇をキッと結び、拳を握り締めた。
『絶対に負けない、負けないわ!』
最後の言葉が境内に響き渡った。
「この次は、胡蝶の記憶を取り戻すんだ…」
全員が空を見上げたまま、誰からともなく、そう呟いていた…。
完全に阿修羅が見えなくなった後、後藤氏が一同を見て言った。
「さて、まだまだ忙しいですぞ。田村君、消防車は?」
「今、携帯電話で連絡しました。クワィロゥが消えたから電波妨害もなくなったようですよ」
その言葉に、急に現実に戻されたような気がした。屋根の上にいたまりちゃんも、静かに舞いおりてきた。堅い決意を込めた瞳を、大きく見開いて。
黙って歩いていると、鈴魅亜の手が肩におかれた。
「心配ない、きっと胡蝶の記憶は取り戻すわ」
「有難う」
その一言に随分と励まされたような気がした。
そうだ…この次は必ず。威追との決着も着けるぞ。
それぞれが色んな思いを胸に、寺の門を通り抜けた。左手からは朝日が上ってきた。まるですべてが悪夢だったかのように。何だか生まれ代わったような気持ちだ。
「あ〜あ、腹減ったなぁ!」
田村刑事が大きく伸びをして言う。それを真似したかったのか、ことだまも大きく伸びをして言った。
「お腹、空いたでちゅ!」
鈴魅亜が微笑んで、足下にいたことだまを抱き上げた。
後藤氏はそれに頷き、丸い目を見開いて言った。
「そうですね。じゃあ一度、火川神社に戻りましょうか」
「是非そうして下さい。氏子さんから戴いた秘蔵のウニがございます」
「おお、それで一杯、やりたいねぇ!」
何だか皆なが活気づいてきたようだ。そうこなくっちゃ。
もう一度、振り返ると、燃え上がった場所には既に消防車がかけつけていた。隊員が必死で消化活動にあたっている。
タクシーを拾うために、大通りまでノロノロと歩く。歩きながら小さくため息をつき、まだ夜の色が残った、朝焼けの空を見上げて僕は思った。そう…悪夢は去ったのだ。
|
|